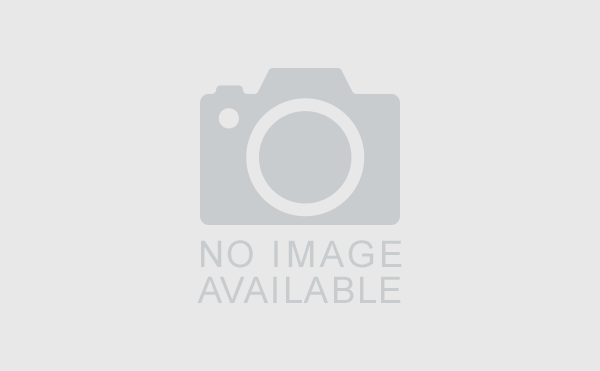予算特別委員会(第3分科会)教育委員会 令和7年3月5日(水)
ゆる部活動を「KOBE◆KATSU」へ活用することについて・子供の権利について・神戸市の教育方針について・自由進度教育進捗について・不登校支援の発信について・リアルケアベビーを使った教育について・電子図書館の利用について・神戸市PTA安全教育振興会の積立金について・SNS対策についての要望
○分科員(さとうまちこ)令和2年度決算特別委員会でゆる部活が世田谷区で実施されていると御紹介させていただきました。これは生徒数減少により運動部の廃部や生活習慣の変化等により、運動不足が課題とされる中、勝ち負けにこだわらずに子供たちが希望する競技を提案し、様々な種目に取り組むというものです。
本市では2026年9月に「KOBE◆KATSU」への移行を打ち出し、子供たちが幅広い選択肢から取り組みたい活動を選択できるようになりますが、先ほど御紹介しましたゆる部活のように、年に一度でも月に1回でも様々な活動に取り組める「KOBE◆KATSU」があってもよいのではないかと思います。
地域の方々には、いろんな文化祭へ行って思うんですけれども、皆さんすごくお上手な方が多くて、例えば、手芸や茶道、囲碁、太極拳、ヨガなど、様々皆さんされております。
これらの活動の指導者、または上手な方を社協やふれまちにリストアップしていただき、それを基に生徒がアクセスし、参加したい生徒を掲示板などで募集し、活動していくと生徒は主体性が育ちますし、地域の方々が教えることによって、多様な生徒の居場所にもなり得ると思います。
また、生徒との交流が生まれ、学校への理解も深まり、地元とのつながり、ひいては後継に悩む地域の活性化にもつながると考えますが、御見解をお伺いいたします。
○竹森教育委員会事務局学校教育部長 様々な提案をいただきました。神戸市におきましても、複数の種目をやってみたいですとか、仲間と楽しく活動したい、そういったふうに考える生徒が増えてございます。
また、保護者のほうも子供のうちはいろんなことを体験させたい、経験させたいと考える方が一定おられます。
そのようなことも踏まえまして、今回のこの「KOBE◆KATSU」ですけれども、もちろん大会への出場ですとか、技術、技能の向上を目指す、そういった活動、それはもちろんなんですけれども、一方で趣味を一緒に楽しむような活動まで多様な活動に広げていきたいと考えてございます。
今回の第一次募集におきましても、御紹介いただいたゆる部活に近いような活動としまして、シーズンスポーツ、季節ごとにいろんな種目に取り組むような活動、こういった提案を実際にいただいてございます。
また、レクリエーション活動ですとか、エクササイズ、それからニュースポーツ、そういった活動も今申請をいただいておるところでございます。
こういった選択肢が増えることは非常に生徒にとっても望ましいことと思ってまして、特に特別支援学級の生徒、こういった生徒の選択肢の拡大にもつながるのではないかと、私ども期待しておるところでございます。
それと、「KOBE◆KATSU」の活動頻度ですけれども、下限というものは設定しておりませんでして、例えば、月1回の活動で参加費はワンコインですよと、そういった活動の申請も実際にいただいてございます。これもそのような活動を広げることで複数種目をやってみたいというような生徒の選択肢も広がるのではないかなと思ってございます。
それからもう1つ御提案いただいた生徒が希望する活動の連絡先に自らアクセスして参加する、そういった御提案ですけれども、これも実は近い形としまして、ダンス、卓球、バスケ、バレーそういった複数の種目の中から生徒が自分の都合に合わせて、日時も場所も、それから回数も選択してアプリから申し込むと、そのような活動についての実際の申請も今いただいておるところでございます。
それから、地域との関係ということをおっしゃいました。これも常々申し上げておりますように「KOBE◆KATSU」の大きな目的の1つが中学生が地域の方々と活動することで、多世代交流、地域の活性化につなげていくということでございまして、このたびの提案でも地域の方々が指導者となる茶道ですとか、手芸、太極拳などの活動はもちろんですけれども、地域でのボランティア活動、それから地域イベントの企画・運営、農業、伝統芸能、そういった実際に中学生が地域の方々と一緒に活動したり、地域で行われている活動に参加できるような申請も多くいただいてございます。
いずれにしましても、今後も多くの方々の協力をいただきながら、生徒の活動機会を確保しますとともに、「KOBE◆KATSU」の活動を通じまして、地域の活性化にもつなげていきたいと思ってございます。
○分科員(さとうまちこ) ありがとうございます。地域の方々と交流を深めるというのは非常によい機会となると思いますので、ぜひしっかりと御検討いただきたいと思います。
また「KOBE◆KATSU」に関しては様々な意見があって、丁寧に進めるべきことではありますけれども、指導力のある優秀な教員が1校ではなく、多数の学校の生徒たちに指導していただけるようになることもあり得ます。それは本当に生徒たちにとってもありがたいことだと思っています。また、優秀な指導者の後継の力不足で生徒の不満が大きくなったり、同時に教員のストレスともなったり、部活内でのひいきが起こり、授業にも悪影響があったという例も見聞しております。
受験のために部活動は必要と思いつつ、あまり活動をしなくてもよいような部活を選ぶといった生徒も増えておりました。生徒たちを成績のための部活動からは解き放って、あとは多くの選択肢の中から自分の好きなものや得意や趣味などを探すことができるきっかけになれば本当にいいなというふうに思います。
また、企業との連携など非常によいことだと思うんですけれども、恐らく中心部での活動になるのではないかということが予想され、今までも出ましたけれども、交通費とかが必要となると思います。やはり子供たちが勉強でも、習い事でも、フリースクールでも、平等に活用できるような、この際、教育バウチャーなどを取り入れていただくように要望いたします。
また、この際、インクルーシブスポーツなどありまして、ボールにオイルを塗ってスポーツすると思うようには絶対打ったり、投げたりできませんので、そういったところで障害者の立場になってプレイするなど、新たな取組など、やっていただけたらと思います。
次に、子供の権利についてです。
先日開催された教育こども委員会では、こども家庭局から神戸っ子すこやかプラン2029(案)に関する市民意見募集結果が報告され、子供向け意見募集の結果が公表されました。
令和5年4月にこども基本法がこども家庭庁の創設と併せて施行され、6つの基本理念のうち、自己に直接関係する全ての事項に対して意見を表明する機会が確保されることが明記されている中、子供向け意見の件数を見てみると4,767件と、小学校4年から中学校3年まで約7万人ほどの児童・生徒数に比べて非常に少ないのではないかと感じました。
今回は、先般の報告を例に挙げましたが、子供たちがしっかりと意見を伝えられる環境をつくり、そして、大人がしっかりと意見を聞く姿勢が大事だと思っています。
子供たちから意見やアンケートを聞く際は、授業の一コマなどを取るなどし、質問の趣旨をしっかりと伝えて様々な意見を言い合える教育を実行していくべきと考えますが、御見解をお伺いいたします。
○田尾教育委員会事務局次長 こども基本法の基本理念に定められている子供たちが意見を言えるという、これに関しましては、子供たちの大切な権利の1つだというふうに我々も認識をしております。
また、アンケートに回答し、自分の声を届けるとか、それから自分の意見が尊重されるといった経験は自己肯定感ですとか、自主性が向上するとともに、主権者意識の基礎を育むという意味でも非常によい経験ですし、様々な効果をもたらすものというふうに認識をしております。
アンケート等で子供たちの意見を聞く際には、やはり大人が発達段階に応じて趣旨を分かりやすく説明する必要がありますし、質問の内容や選択肢等について、きめ細やかな配慮や工夫が必要だというふうに思っております。
子供たちの意見に対して大人が真摯に向き合い、学ぼうとする謙虚な姿勢もおっしゃるとおり、大切だというふうに思っております。
教育委員会といたしましては、このこども基本法の趣旨を踏まえまして、今申し上げたことに十分留意をしながら、子供たちが主役となって対話を大切にした教育活動を一層推進してまいりたいというふうに考えております。
○分科員(さとうまちこ) こどもまんなかとかアドボカシーとか言いながら、なかなかの実行にはつなげていくのはもう難しいのかなというふうには考えておりますが、どうぞ今後ともしっかりよろしくお願いいたします。
今回、アンケートを提出した児童・生徒たちは、きっと何事にも積極的に関わっている子たちなのかなというふうに思うんですけれども、それをやらない子供たちの意見を聞くことが非常に重要だと感じております。
今回、こういったアンケートを取ったということで、教員によるわいせつ行為なども重大な問題となってきておりますので、そういったことがないかどうか、子供たちが安心して学校生活を送れるよう、早期の問題解決のためにもアンケートを使うのも有効だと考えます。
ぜひ、待つのではなく、意見を引き出して持ってこれるような工夫もお願いしたいと思います。
次に、神戸市の教育方針についてです。
昨年度末に第4期神戸市教育振興基本計画が策定され、先5年間の神戸市の教育方針が示されました。
内容としては、実施すべきだが、当たり障りのない事柄ばかりなので、神戸市の教育がこれから何をしていきたいのか、市民、保護者には伝わりにくい、響きにくい内容だなというふうに感じました。
これまでも紹介してまいりました石川県加賀市の方針は非常に分かりやすく、これまでの教育の問題点とともに目指すべき教育が明確に示され、保護者と児童・生徒の興味を引き、そして新入生や不登校児童、または潜在の不登校児童にも希望となるような内容になっていると思いました。
本市の教育が目指す目玉、具体的で共感できる方向性を神戸市の教育が変わると、もっと外向けにアピールし、打ち出すべきだと思いますが、御見解をお願いいたします。
○福本教育長 今、議員から厳しい御指摘をいただきました。
第4期の神戸市教育振興基本計画につきましては、御紹介いただきましたように今後5年間、どのような力を育んでいくか、保護者と市民の皆様と共有して共に進めていいただけるような新たな教育ビジョンとして、自他を大切に、自ら考え、未来をつくるという形で今進めさせていただいております。
それを展開するために5つの方針を決め、またそのそれぞれに幾つかの重点な取組を示しています。リーフレットを持ってきたんですけれども、これですよね。
これを見ますとで、全部で40近くになって、確かに言われましたように、中には具体的なものをもあれば、ちょっと概念的なものというものもあって、やはり子供たちや保護者にとって日々の学校生活や教育活動においてどんな変化が起こるのかとか、そういうものが直接的に、具体的に分かりにくい、そのようなことは御指摘のとおりかなというふうに思います。
したがいまして、やはりこれはしっかりと神戸市が決めた方針ですので、まずは広報をして、できるだけ多くの関係者の皆様と共有できるように工夫したいと思います。
その上で、特に7年度について、やはり今我々としては特に子供が主役の学び、個別最適な学びと協働的な学びの充実を目指して、とにかく授業を変えていこうと、授業改善するんだということで各教員に促していきたいと考えております。
先ほど1つ答弁にありましたが、それに加えてやはり実践的なコミュニケーション能力の習得を目指した英語教育、ここにも非常に力を入れてやっていきたいなというふうに考えております。
いずれにしましても授業を変えるということになりますと、やはり今までとは違うわけですから、学校長にリーダーシップを発揮してもらって、そのような形の子供が主役の授業ということを教育委員会としても組織編成、変えるということを先ほど言いましたが、そういう形を取って、しっかり伴走して目指していきたいと、そのように考えております。
○分科員(さとうまちこ) 自由進度についてもきっと進められていく、前はモデル校をというふうにおっしゃってはおったんですけれども、やはりこれは賛同はいただけているし、やっていかれると思うんですが、進捗状況というのをお聞きしたいと思います。
また、多くの学校長ですとか、教員の方々が加賀へも視察へ行ったと思うんですけれども、その感想とかもし分かりましたら、そのあたりちょっと端的にお聞かせいただきたいと思います。
○田尾教育委員会事務局次長 自由進度学習でございますけれども、確かに現場の教員などもたくさんの教員が視察に行きました。
やはり取り入れられるところからどんどん取り入れていきたいというようなこと、非常に前向きな意見を聞いております。
自由進度学習という名前にこだわるのではなく、やはり学習の中で子供たちが自己決定できる、学び方を自己決定し、それをまたやってみて、それがどうだったのかということをしっかり反省をして自己調整をしていく学習ということを神戸市としては進めていきたいなというふうに思っております。
○分科員(さとうまちこ) 「KOBE◆KATSU」についても現場の教員の方々がちょっと驚いていたようなこともありまして、なかなか現場の浸透というのが難しいのかなというふうにも感じております。
やっぱり今までの一方的に教える教育じゃなくて、児童・生徒と伴走するという教育に力点が置かれつつあると思うんですけれども、これもまた現場の先生方に伝わってないのではないのかなっていうふうに感じております。
また、そういった教員に伝わっておらずに学校も変わっておらず、本当にこれ1つ1つはすばらしいことが書いてあるんですけれども、そういった共通の大きな認識というか、課題とかっていうのもなかなか共有するのも難しいのかなっていうふうに現場の先生方とお話ししても思いますので、このままではやっぱり今、不登校児童の子がじゃあ学校行こうかなというふうに、例えばこういうふうに、加賀、何度もお見せしてますけれども、なぜ今教育を変えるのかとか、こういうふうに変わりますとか、計画みたいなものをしっかり明記されているんですね。そういうふうなアピールをしっかりとやっていただきたい。目標とかそういった思いに関しては一緒だと思いますので、ここはやっぱり今まで不登校を経験したことない教員の方っていないと思うんですね。なので、教育改革は必須だと、こういうふうにやっていきますよということは分かるんですけれども、やはりさらに学校が子供たちにとって安心できる場所なんだよっていうアピールをする上で、やはり主体である子供たちが、こういうのを見て響くような内容のものをしっかり発信していただきたいと思います。
も他の自治体のことは取り入れつつも、さらに神戸はよい内容に進んでいっていただきたいと思いますので、教育長、ぜひさらに汗を流していただきたいというふうに思います。
次に、不登校支援の発信についてです。
不登校、または潜在的な不登校児童・生徒のことで悩んでいる保護者は多く、この悩みは非常に深いものとなっています。どんな支援があるのか、どこに相談したらいいのか、疲弊しながら情報を探しております。担任に聞けたらもちろんいいんですけれども、担任や学校に不信感を持っておられればそれも難しいこととなります。
不登校支援に関する情報は市のホームページで個々の支援内容を掲げておられますが、文章のみで情報が多く、全体像がつかみにくいものとなっております。
保護者が求めるのは自分の子供の現在の状況に対して、どのような支援が受けられるのか、文章ばかりでなく、一目で視覚的に確認できるよう、ホームページをリニューアルされてはいかがでしょうか。すいません、端的にお願いします。
○小菅教育委員会事務局部長 不登校支援の発信についてでございますけれども、これまでも本市におきましては多様な学びの場の確保、それから積極的な情報提供等も含めまして支援、発信を続けているところでございます。
実際に本市のホームページでございますけれども、不登校支援の相談窓口、それから施設、各施策の取組、カテゴリーごとに情報を今まとめて掲載をしておるんですけれども、委員御指摘のとおり、個々の支援策を網羅的にまとめている状態でございますので、全体像が分かりにくいものであることは課題として認識しておりまして、今後、視覚的に分かりやすく、情報をまとめて発信できるように検討を行っているところでございます。
いずれにしましても今後も不登校支援策の充実に取り組むとともに、支援を必要とする保護者、児童・生徒に分かりやすく情報を届けられるよう情報発信に取り組んでまいりたいと考えてございます。
○分科員(さとうまちこ) ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
例えば、分校や学びの多様化学校へも転籍手続が必要であったり、不必要であったり、一般的には非常に分かりにくいものとなっております。そういった内容も明記しつつ、かつシンプルに可視化していただきたいと思います。
次に、高校生の育児体験についてです。
厚労省のデータによりますと令和3年度の人工妊娠中絶件数を20歳未満で見ると、19歳が4,051件と一番多く、次いで18歳が2,466件となっております。高校生にもなれば身体的に性機能が成熟するとともに異性への関心が高まり、正しい知識がないまま安易な性交渉によって若年層の望まない妊娠につながっているのではないかと考えます。
もし妊娠して子供が生まれたらどう育てていくのか、実体験に近い学びを行うことは有意義であり、重要なことであると考えます。
そこで、他都市でも実施しているリアルケアベビーを使った授業を実施してはどうか見解をお伺いいたします。
○田尾教育委員会事務局次長 中学校、高校の家庭科の授業の中で、平成20年度に今御指摘をいただいたようなことを背景に、できるだけ子供の成長発達のところを学ぶ保育領域の学習の中で、実体験を伴うような学習をするということが位置づけられています。
それに伴いまして、神戸市では全国に先駆けて中高校生を対象にしてプレ親学習授業というものを展開しておりまして、中学校では必修、高等学校では可能な限りということで、近隣の保育施設等とタイアップいたしまして、実体験を推奨しております。
事前学習として、このようなAIの保育人形ではありませんけれども、新生児人形を活用したりですとか、それから妊婦の疑似体験、そういったことなんかもしながら、できるだけ実体験に使えるような学習を進めていこうというふうにしているところで、それは現在も引き継がれているというところです。
ただ、おっしゃるように、こうした新しい教具などもやはり出てきておりますので、そういったことについてはこれからも情報をしっかりとこちらのほうとしても集めまして、もっともっと工夫できるところがないかというようなことは考えてまいりたいというふうに思います。
○分科員(さとうまちこ) ありがとうございます。プレ親は私もPTA会長しているときにもお手伝いをいっぱいしたり、記憶はあるんですけれども、コロナ禍でも心配していたように妊娠中絶って増えたんですね。やっぱりもっとできることをどんどんどんどん子供たちにも分かっていただいて、実施をしていただきたいと思います。
実は、中学校でやっているということで、大阪市の中学校で重さ3キロの人形で、実際の乳児のようにミルクとオムツ交換、だっこを求めてランダムに泣き出すという、抱き方やあやす頻度、体温調節といった世話の状況が記録されます。
この授業では命の大変さを考えるとともに、相手を思いやる気持ちを高めることを学び、そして、児童虐待防止も目指しております。
核家族化し、子供の成長を間近に見られない環境もあり、実際心身ともに傷つくのは女子生徒ということもあります。全員に体験することが難しければ、長期休暇の前のときなど、ちょっと手を挙げていただいて、その様子とか感想などをオンラインで共有するなど、社会生活に役立つ、実る体験をしてもらいたいと思っています。
そして、電子図書館の利用について入学時に家庭の事情に左右されず子供たちが全員いつでも電子図書を閲覧できるよう配慮すべきと提案させていただきましたが、もし進捗があれば、端的にお伺いいたします。
○西川教育委員会事務局部長 電子図書館についてでございますけれども、児童・生徒がいつでも本が読める環境を整えるために学習用パソコンを活用して電子図書館をより簡易に利用する仕組みを構築できないかといいますことを他都市の事例等も参考にしながら、市立図書館とともに検討を進めてまいりました。
現在、市立小・中学校の児童・生徒に対しまして神戸市電子図書館の読み放題コンテンツを利用できる専用IDを発行する準備を進めております。読み放題コンテンツは、同時に複数での接続が可能であり、授業での一斉読書などにも活用できます。来年度の早い段階での利用開始を目指している状況となっております。
今後とも、児童・生徒がいつでも読書できる環境を整えまして、本に親しむ機会を増やす取組を一層進めてまいりたいと考えております。
○分科員(さとうまちこ) デバイスにショートカットアイコンみたいなのを置いて、いつでもアクセスできるようにしていただきたいということを提案したと思うんですけれども、その際に、親の許可といいますか保護者の承認がないと、なかなかそういうことってできないっていうふうにお聞きしたので、デバイスでみんなに見れるようにしたら不登校になったときでも本に手が伸ばせるのではないかというようなことだったんですけど、それは、もうもともとデバイスに入れていただいて、親の承認関係なく見れるというものになるんでしょうか。
○西川教育委員会事務局部長 個人情報というのはちょっと置いておきまして、学校何クラスの何番といったような出席番号でのやり取りという形で聞いておりますので、特に子供たちが端末を使って読書をするということに関しては問題はないかなというふうに考えております。
○分科員(さとうまちこ) ありがとうございます。
次に、神戸市PTA安全教育振興会の積立金についてです。
神戸市PTA安全教育振興会の積立金は7,000万円ほど積み立てており、その使途は具体的に決まっていないとお聞きしています。
PTAから脱退する学校も年々増加傾向にあり、この4月でもう激減するのではないかと思っています。
学校に返金や、例えば「KOBE◆KATSU」などに活用するなど考えがいろいろあると思うんですが、今、この積立金に関して、何かお考えがあったら、お聞かせいただきたいと思います。
○竹森教育委員会事務局学校教育部長 このPTA安全教育振興会でございますけれども、PTA会員のための保健事業制度として1993年に設立されてございまして、PTA活動中のけがとか事故があった場合の見舞金が支払われているということでございます。
加入者は1世帯当たり年間100円負担いただくということでございます。
御指摘のとおり、この振興会の会計年度において余剰金が生じた場合に、特別会計として積み立てるということになってございまして、現在、その積立金が約7,000万円ということでなってございます。
教育委員会としましても、高額な余剰金が毎年度繰り越されるということは適切ではないと思ってございまして、市全体としまして子供たちのために何か還元していくこと、そういったことを早急に検討していただく必要があると認識してございます。
現在、この積立金の管理について定めております規定の中に、積立金に係る具体的な使い道が記載されていない状況でございますので、そのため、まず振興会のほうで積立金の使い道についてもちろん御検討いただいて、規約改定などの手続を進めていただく必要があると考えてございます。
教育委員会としましても、振興会の意見を尊重しながら、より適切に運営されるよう支援していきたいと考えてございます。
○分科員(さとうまちこ) PTAもなかなか存在も危うくなってきたところで、私も払ってきましたし、これからこのまま消えてしまうようなことはないと思うんですけれども、今の間にPTAでいたOBの方とか、あと今現在いらっしゃる方々で検討、議論を進めていただきたいというふうに思います。
そして、リアルに体験できる教育プログラムというものがあります。前も、こども家庭ですけれども、そういったスマホの使い方のそういったこともしてて、高校生が中学生に教えるということで非常に身近に感じて非常に有意義なものだったんじゃないかと思います。
リアルに体験できる教育プログラムですが、SNSでの勧誘から抜け出せない恐怖までリアルに追体験ができる教育プログラムとなっています。ぜひこれも神戸市で取り入れていただいて、全校での実施が難しいとしても、やはりこのプログラムを体験する様子を全校で見られるようにしていただきたいと思いますが、こちらに関してはいかがでしょうか。
○田尾教育委員会事務局次長 今御提案いただいたプログラムに関しまして、申し訳ございません、私、不勉強でしたので、しっかりと学んでみたいと思います。
○分科員(さとうまちこ) やはりいざこういうことに手を出したら非常に恐ろしいんだよというようなことが実体験できるプログラムとなっておりますので、ぜひ検討いただきたいと思います。
そして、以前も難しい授業については動画を使うべきではないかと提案させていただきました。今後、子供たちにも理解しにくい授業ですとか、分かりにくい単元をアンケートなどで募り、理解しやすい動画、教えるのが上手な先生の授業を共有していくような方向にも持っていっていただきたいというふうに思います。
最後、不登校の抜本的な対策としては、やはり公教育の非常に重要性というのが考えられております。自由進度学習やイエナプラン、学びの多様化学校などありますけれども、こちらもなかなか進んでいないように受けております。
また、このあたりだと、今、サポート教室であるとか、最近できました学びの多様化学校などからも、そこにも属することができない生徒たちが3,000名ほどということになっています。その子たちは部活動にも参加できませんし、いろんな教員の方々の接触もないということになっております。今お伝えしましたゆる部活―― ゆる部活と呼ばなくてもいいんですけれども、そういったことに関しても不登校の子供たちにしっかりと情報を行き渡らせていただきたいというふうに思います。