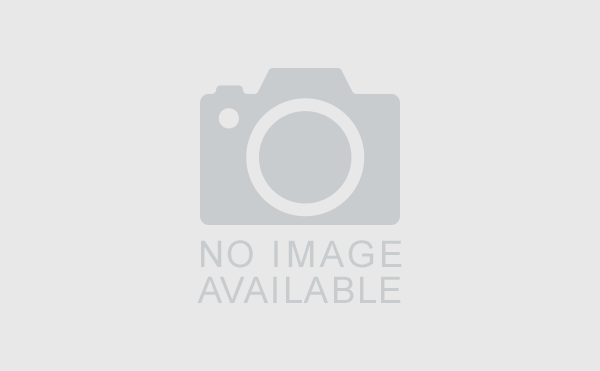部活動は不要と考えます。
今まで重ねてきた質疑の総まとめともなっていますが、どなたかの何かのご参考になれば幸いです。
本市では、2026年9月から「KOBE◆KATSU」への移行を進め、子どもたちが自らの興味・関心に応じて、幅広い選択肢の中から取り組みたい活動を選べるようになります。
現在、さまざまな団体にご参加いただく予定ですが、あわせて、年1回や月1回でも地域の方々と協力して多様な活動に取り組める「KOBE◆KATSU」の形も推進しています。
文部科学省も部活動の地域移行時において推奨しております地域との連携です。地域には、手芸、茶道、囲碁、太極拳、ヨガなど、さまざまな分野で活躍されている方々が多くいらっしゃいます。これらの指導者や熟練者を、社会福祉協議会やふれまちなどでリストアップしていただき、その情報をもとに、生徒が主体的にアクセスし、参加希望者を掲示板などで募って放課後に活動を行うというような仕組みを整えることで、生徒の主体性が育まれます。
また、地域の方々が指導に関わることで、多様な生徒の居場所づくりにもつながり、交流を通じて学校への理解や地元とのつながりが深まり、後継者不足に悩む地域の活性化にも寄与すると考えます。
「KOBE◆KATSU」に関してはさまざま意見があり、丁寧に進める必要はありますが、今後、指導力のある優秀な教員が1校にとどまらず、複数の学校の生徒たちに指導できる体制が整う可能性もあります。これまでは、優秀な指導者の後継不足により生徒の不満が高まったり、教員の負担増や部活動内の不公平が授業に悪影響を及ぼす例も見受けられました。少子化により部員数を満たさないため部活そのものがなくなったり、逆に部員過多となり、活躍の場を見出せない生徒もおりました。
塾通いなどの受験対策のために「活動の少ない部活」を選ぶ生徒も少なくありませんでしたが、今後は、生徒が成績や受験のためではなく、自らの興味・特技・趣味をもとに活動を選び、自己探求や自己表現のきっかけとなることを期待しています。
今後、企業との連携が進む場合には、交通費などの経費も必要となります。そのため、日本維新の会神戸市議団では、子どもたちが学習・習い事・フリースクールなど、あらゆる学びの場で平等に活用できるよう、「教育バウチャー制度」の導入を要望しています。
不登校対策として、サポート教室や学びの多様化学校、フリースクールなどが設置されてはおりますが、これらにも通えない生徒が3,000名以上存在します。こうした生徒たちは、現在、部活動への参加や多様な教員との関わりの機会も持てておりません。地域移行を進めるにあたっては、不登校の子どもたちにも情報をしっかり届け、全市で多くの生徒が参加できるようにすべきです。
依然として学級崩壊や不登校の課題は山積しており、文部科学省も一斉教育の限界を指摘される中、本市でも、個別最適な学びとして「自由進度学習」を推進していますが、実現のためには教員研修の充実や、一定の準備期間が不可欠です。
教員の方々には、学級崩壊や不登校の根本的要因である授業改善に全力を注いでいただくためにも、部活動の地域移行については速やかに実施していくべきと考えます。
部活には様々なマイナス面もあったことから、今こそ、教員も生徒も部活動から解き放たれ、新しい時代に、新たな道を切り開く道を模索できる大切な機会だと捉えています。