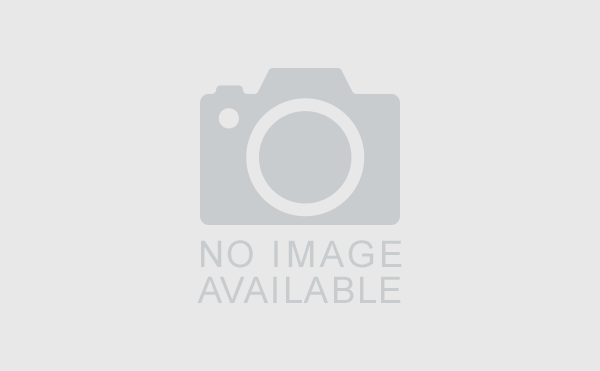ゆる部活について(2020-03-06)の質疑抜粋
東京都世田谷区中学校での「ゆる部活」は、2018年より実施されています。
生徒たちの自主的な活動を促すもので、この辺りから、部活動に参加できていなかった生徒たちへの策として、地域の方々に学校へ入っていただき、生徒たちと交流しながら書道や花道、お茶、絵画、ちぎり絵、囲碁など教えてもらえたらと考えていました。
地域の方々に、「部活の地域移行になった時は、学校へ来て生徒たちに教えてあげてくださいね」と言うと、「私なんてとてもとても!」とおっしゃいますが、「話し相手でもありがたいです。生徒たちの居場所になります。」とお伝えすると、よく、それもそうだなぁと言う表情をされておりました。
よく、各地域の文化祭にお邪魔するのですが、プロ!と思える方々の力作が並んでおり、「私が仲介して売りましょうか?」などと冗談を言っていたものです。そこからもヒントを得ました。文科省も、地域の方々との連携を両輪としながら部活動の地域移行を進めたいとの答弁もありました。
生徒がいろんなことにチャレンジする機会を増やし、今よりもっと得意な事とか、楽しいと感じることのできる趣味が見つかれば良いと思います。少なくとも、今のままの部活では、ほとんどの生徒にそれが感じられません。
もっともっと、地域と学校との流動性を作り、どの生徒にとっても大切な<居場所>になって欲しいと思います。
分科員(さとうまちこ) 次に,柔軟で多様な部活動のあり方についてお伺いいたします。
平成30年3月に,スポーツ庁が運動部活動のあり方に関する総合的なガイドラインを策定し,神戸市もそれにのっとったガイドラインを策定,週当たり2日以上の休養日を設けるなどを定めております。
スポーツ庁によると,ガイドラインにおいて,子供のニーズを踏まえた環境整備の重要性がうたわれているとおり,運動の得意・不得意にかかわらず,子供たちが楽しめる居場所としての部活の需要が大きいことから,ゆる部活の取り組みが推奨されております。
ゆる部活とは,競技志向の強い今までの運動部活動とは異なり,体力向上や運動の楽しさを実感するための新しい部活であり,活動状況はさまざまでありますが,他都市では体力向上部やレクリエーション部などがあります。子供たちの多様なニーズに対応しながら,居場所となり,体力の向上にも資するなど,有効なものがあります。
例えば,地域と連携し,顧問を引き受けてもらうなど,工夫しながらこの取り組みを積極的に進めていくべきだと考えますが,見解を端的にお願いいたします。
藤原教育委員会事務局学校教育部長 今,先生御紹介いただきましたスポーツ庁のWeb広報マガジンにもそういった記載もありまして,確かに需要はあるというふうに考えてございます。
本市におきましても,高等学校ではございますが,葺合高校の野外活動部や,摩耶兵庫高校のウエートトレーニングなど,競技とか,そういう優勝を目指さない形での活動がございます。部の創部ということになりますと,本市では平成30年に中学校の部活ガイドラインを策定しておりまして,その中で,創部・廃部といった部活動にかかわる課題について,教職員や保護者等によって構成される部活動検討委員会において議論した上で,創部・廃部を決めるという形になってございます。
ですので,そのゆる部活動を創部する場合は,まずは学校で十分議論していただく必要があるのではないかと考えておりまして,もし仮に創部ということになりましたら,その上で,学校からニーズがあれば,教育委員会として部活動指導員の配置など,支援を行っていくことは可能ではないかと考えてます。
今後でございますが,そういった競技志向ではなく,レクリエーション志向で行うゆる部活動については,具体的にどのように運営されて,どういった効果が生徒にあったのか。また,先ほど申し上げた学校で議論していただくために情報収集も必要でございますので,他都市の事例等をよく研究していきたいと思ってございます。
分科員(さとうまちこ) 他都市の事例はもう出ておりますので,スポーツ庁の鈴木大地長官も,スポーツの幅はこんなに広いのだということを伝えていく必要があるとお話もされております。あと,世田谷区のある中学校の軽運動部は,月2回ほど,文化部で体を動かすことがない生徒なども入部しております。リズムに乗ってパンチを繰り出すボクササイズや,2本のロープを使って跳ぶダブルダッチ,チアリーディング,ミニテニス,バランスボールの体幹トレーニングなど,異なる種目を楽しんでおります。
たしか,神戸市の中学校にも,PTAの講師の一覧のようなものが冊子であったと思うんですけれども,それで無料で教えていただけるような方も,かなり地域の方でいらっしゃったと思います。教育委員会のほうから,こういったこともあるよということを提案されて,そして中学校のほうで,生徒のニーズを聞いて,生徒の自発的な発言をもとに進めていくということにはなりませんでしょうか。
藤原教育委員会事務局学校教育部長 先ほども申し上げたように,少しやっぱり議論なりしていく必要がございます。やはり,どういったふうに運営されて,どういった効果があったのか,もう少し研究をさせていただければと思います。
分科員(さとうまちこ) そうですね,まずやってみたらというふうに提案していただくのも1つの手かと思うんですけれども,ちゅうちょされる意味が,ちょっと私には理解しかねます。
運動部ではないですけれども,ほかの部活をつくって,積極的にその活動を支援されている校長先生も,かつて──直近におりましたので,ぜひそのあたり,今のニーズを考えていただいて,教育委員会のほうから積極的に動いていただきたいと思います。