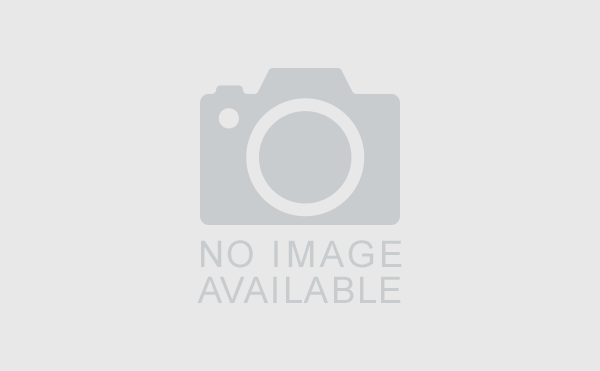2025/9/18いじめ加害者への対応について
以前より質疑を繰り返してまいりましたが、被害児童生徒の学ぶ権利を守るためには、制度的に優先して指導・措置を講じる仕組みが必要ではないか。被害者が不登校、転校を余儀なくされていないか。市として、加害者への別教室指導や登校停止といった対応を制度的に位置づけ、被害者が安心して学べる環境の保障をすべきだと質疑を繰り返してきたが、その後どうか。
西川教育委員会事務局部長 神戸市のいじめ未然防止学習におけるオリジナルの学習指導案の作成を少しお話をさせていただきたいと思います。
児童・生徒がいじめ問題を自分事として捉え、考え、議論できるような内容としまして、自己指導能力の育成を目指しております。いじめは決して許されないことであることを学ぶことはもちろんです。児童・生徒が自分の大切さとともに、他の人の大切さを認めることができる人権感覚を身につけるよう働きかけることを最重視しております。
中学3年生の内容ですけども、法的な観点を含めた学習内容としておりまして、児童・生徒の年齢によっては理解が難しい側面もあるため、発達段階に応じたいじめ未然防止の学習を低学年から継続して行うことによりまして、児童・生徒のいじめ防止に対する理解や意識を高めてまいりたいと思っております。
いじめ対応につきましては、神戸市いじめ対応のための実施プログラムに基づくいじめ対策を進めておりまして、今後、本プログラムの実施状況等の検証を行っていく中で、社会情勢等を考慮しながら、発達段階に応じたいじめ防止学習となるよう、いじめ未然防止に資する取組を推進してまいりたいと考えております。
さとう 文科省のホームページにも出ております「学校において生じる可能性がある犯罪行為等について」というページもあるんですけれども、これ、漢字が読めたら理解できると思うんですね。ぜひ中学校以上は、最低でも教室に貼ってもらったら読んでくれるかなと思いますので、そういったことからでもお願いしたいと思います。
メモ:「いじめは成長過程の通過儀礼だ」というのは極めて危険な誤解です。この言葉は、被害を受けている子どもの苦しみを矮小化し、本来であれば社会全体で取り組むべき深刻な問題を個人の問題へとすり替えてしまいます。
いじめは、単なる子ども同士の「ケンカ」や「からかい」とは本質的に異なります。その定義には、国際的に共通する三つの重要な要素が含まれています。
「意図的な加害行為」「繰り返し」「力関係の不均衡」が存在することです 。この力関係の不均衡こそが、いじめの最も悪質な点です。
被害を受けた子どもは、自力でその状況から抜け出すことが極めて困難な状態に置かれます。いじめの形態は、殴る蹴るといった直接的な身体的いじめ、悪口や脅しなどの言語的いじめだけでなく、仲間外れや無視、悪い噂を流すといった、目に見えにくい関係性のいじめ、そして近年深刻化しているインターネットやSNSを介したサイバーいじめなど、多岐にわたります。いじめられた経験のある子どもはもちろんのこと、いじめられた経験もある子供が非関与者に比べてうつ病リスクが3.19倍にも上る。
「安心感の崩壊」「他者へ信頼ができなくなる事」「無価値感の内面化」など子どもたちの人生長期間に及んで影響があります。
いじめは子どもの心と体に深刻な影響を与えますが、それ以上に影響を与えるのは学校の対応です。学校による不作為や隠蔽は「制度的裏切り」という形の二次被害を生み出し、その心理的ダメージは、時に家庭内での大人による虐待をも上回るほど深刻なものとなり得る。