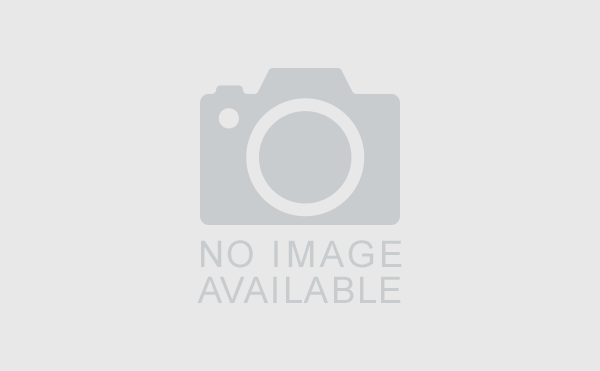2025/9/18教育委員会質疑 自由進度学習について
分科員(さとうまちこ) 早速よろしくお願いいたします。
先ほども教育委員会の評価の中でも、自ら学び、自ら考え、主体的に行動しというふうなことに取り組んでいくというふうな文言もありました。すごくいいことだと思っています。
自由進度学習についてお伺いいたします。
さきの常任委員会で自由進度学習の導入スケジュールについて質疑したところ、直ちに全学校の授業を一斉変更できるものではないという答弁がありました。一斉授業を見直し、新たな学びが進められていると思いますが、このペースでは子供たちは成長し、そういった自由進度学習を受けられずに義務教育を卒業することとなってしまいます。一部の学校の子供たちが恩恵を受けるのではなく、神戸市全ての子供たちが受けられるようにスピーディーに進めるべきであり、授業改革に対して期待している保護者に示してほしいと考えますが、御見解をお願いします。
田中教育委員会事務局部長 これまでの一斉指導型中心の授業スタイルを見直しまして、今新たに取り組んでおります自由進度的な学習のスタイルなんですけども、これは、学び方の1つの手法でございます。児童・生徒が主体的に考え、選んだりする場面は、全ての教科の全ての単元で行うというのではなく、教科の特性や単元の内容、児童・生徒の到達度や理解度を教員が的確に把握しまして、その状況に応じて、より児童・生徒の学びが深まる場面で行う必要がございます。
どのような場面で児童・生徒が主体的に考える機会を設定するのか、どのような教材が望ましいのか、そういったことを学びの質の向上につながるように教員自身も十分に授業研究・準備を行う必要がございます。その研究が不十分で、形ばかりを急いで導入した場合には、学びの質の確保ができないという懸念もございまして、1学期、指導主事による全校学校訪問によって、学校と教育委員会が一体となって授業改善を進めているところであります。
また、いろんな機会を捉まえて教員が学べるようにしておりますので、こういったことを教育委員会だより等で発信していきたいと思っております。
2025年夏に出版された本がありまして、広島県の前教育長が書かれた本なんですね。そこの中で、イエナでも何でも日本の画一的一斉授業のアンチテーゼを示すことが大事だと思う。いろんな意見が来て反発もあるので、少しずつ変えていきたいというのが本音であろうし、イエナプランとか、そういうものではなく、独自のものを開発したいというような方も多いとは思いますが、それでは成し遂げられない。最初の型の体得がない限り、独自のものというのはその先にあるもので、なかなか進まないんですね。結局、やり方が、前が慣れているということで戻ってしまうということも考えられます、十分に。というわけで、反発のない、皆さんが同意する改革なんていうのは全く存在しないと思いますので、そこはやはり教育長が旗を振っていただいて、これからしっかりと自由進度をやっていくということを掲げてほしいんですね。
その中で、今、神戸市では、こういうふうにいろんなみんなでつくる―― 前もお見せしました。ちょっと総花的なものもあります。この中で理解ができないというところがあると思うんですね。
文科省も、なぜそうしなければいけないかというのはホームページにもこういうふうに出しております。今までとは違う、これからこうなるというふうにも出ておりますし、じゃあどうして変えるのかな、中にはいろんな子供がいて一まとめにはできないから、今までの授業には問題があるんですよと。だから、障害をお持ちの子、いろんな子がいらっしゃいます。不登校の子もいれば、家に本があるのが少ない子供とかもおりますので、そこはしっかり変えていかなければいけないのよということは文科省も出しているんですね。
何度も出しますけど、加賀市が何がいいかといったら、大きく、なぜ変えなければいけないのかというのを1ページに出してきています。神戸市は、こうしていきます、こうしていきます、こうしていきますということでは、なかなか頭に残らないと思うんですね。こういうふうに、なぜ今、教育を変えるのかという、今、教育現場が抱えている問題点をしっかり上げていただいて、市民の方や保護者の方にしっかり―― これを読んだだけで、そうか、じゃあ変えなきゃいけないね、部活の問題もあった、そして不登校の問題もあったり、一斉授業では半分以上の子供たちがついていけない、分からないで不登校にもなっていくというような、文科省、これまたデータも出しておりまして、その中では、教師に対する不満ではないですけれども、ちょっと問題があったとか、教師が怖いとか、そういったこともあるんですね。
だから、今までの授業の雰囲気を変えようと思えば、やはり自由進度に矛先を向けなければいけないということはもう明白ですし、そこを一斉にやりますということが非常に大事だというふうに、恐らく皆さん認識していただいているのではないかなと思います。
いろんな抵抗ですとか前例踏襲で難しいと、前、教育長からも御答弁いただきましたけれども、ここはもうKOBE◆KATSUでもいろんな反感とかある上に、またこれも―― これは、本当に生徒に必要なことなんですと。今の4,000人超える子供たちを引き出していきたいと。これから入ってきた子は、ずっと不登校にならなくて学校で学ぶことが楽しいですとか、先生との信頼関係を築いて何でも相談できる、そして解決もしていけるというような、そういったオープンな雰囲気にしていかないと、私はこれ、なかなか変わらないですし、まずは旗振っていただくというのが重要であることをずっと申し上げておりますので、ぜひいろんなやり方でとか、自由進度も取り入れながらと、分かるんですけれども、ここはしっかり方向性を示していただいてお進めいただきたいですし、なぜかという問題点はやっぱり最初に共有をしていただきたい。
不登校を出したことのない先生とか、生徒に100%理解させられた先生というのもいないんじゃないかなと思うんですね。 その中で、前も、教育講演会では、講師が授業をよくしようと思えないなら教師を辞めたほうがいいと言うこともありました。私も、教員の本質を考えると全くそのとおりだと思っています。ここはしっかりついてきていただいて、今年度中にでも体制を整えるなり、いろんな研修とかされているんですから、あとはもうぶっつけでやっていく、問題があったら学校内で、内容、問題を共有していくというようなコミュニケーションも生まれる、対話も生まれると思いますので、しっかり進めていただきたいと思います。
文科省のアンケートでは、不登校の理由としても「授業についていけない、わからない、先生と合わなかった、怖かったなど」とある。
「いろんな意見が来て反発もあるので少しずつ変えていきたい」というのが本音だろうし
「イエナプランとかそういうものではなく独自のものを開発したい」という人も多い。
が、それでは成し遂げられない。
最初の型の体得がないかぎりなかなか「独自のもの」なんてできない。すぐに元に戻ってしまう。反発なしの改革なんて多分存在しない。
と、学校はここまで変えられるの平川理恵さん(前広島県教育長)の著書のお言葉も一部お借りしました。