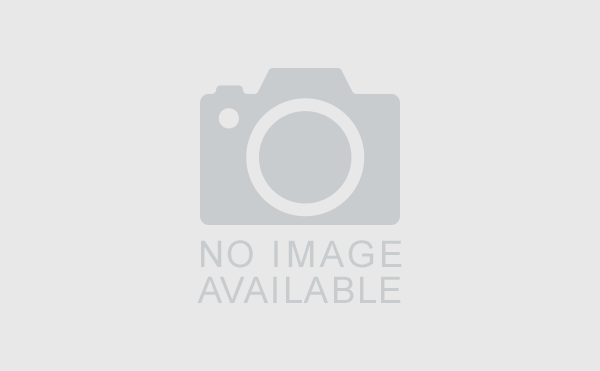2025/9/3こども家庭局の所管事項について
○委員(さとうまちこ) 子育てしやすいまち神戸をアピールするために、三宮第2期整備計画で予定している再開発ビルの中に、流山市のように保育として預けることができる送迎ステーションや、モザイクにあるdakko roomのような一時預かりを行う託児施設を入れてはどうかと考えますが、御見解をお伺いいたします。
○若杉こども家庭局副局長 まず、保育施設の整備の必要性というところでございますけれども、まず利用定員が利用の見込みを上回っているという現状でございます。三宮再整備のエリアでの御提案でございますけれども、そういった状況でございますので、保育の送迎ステーションの新たな整備、施設整備というのは、今の段階では計画していないというところでございます。
もちろん局所的にニーズが高まるというようなことがございましたら、その状況に応じて見直しをしていくというところでございます。
また、一時預かりの御提案につきましても、この点につきましても、事業者で実施の有無を判断するというところで、今そういった事業者からのお声はいただいておらないんですけれども、委員御指摘の三宮再整備、これから第2期のことになろうかと思います。もう少し先の話でございます。先般の外郭団体に関する特別委員会でも都市局のほうが、これから利便性であったり、そのビルの機能を、相乗効果を踏まえながら検討していきたいというような御答弁があったというふうに承知しております。我々としても、都市局と今後に向けて必要な意見交換なりはしていくことなのかなというふうに考えております。
○委員(さとうまちこ) 子育てしやすいまちということですので、かゆいところに手が届くような施策というのは進めていただきたいですし、こういうところにこそ子育て目線というのが必要なのかなというふうに思います。
子供を預けていただいてちょっとゆっくりお茶したりですとか、少し一人の時間を楽しめるような時間というのを神戸では取れますよというような姿勢が本当に欲しいなと。流山市はそういうことをしっかりできているなというふうに思いました。
また、再整備の中で本当に子育て視線というのが足りないのは第1期もそうですけれども、今ちょっと図書館の8階か9階かのちょうど対面に、まだ使用用途が決まっていないような神戸の持分の床がありますので、そのあたりも本当は子育てに何か寄与するような使い方をしてほしいんですけれども、いかんせん、水回りのほうの設計とかが今からできないというようなこともありますので、第2期にはしっかりそういった視点を入れていただきたいし、市が率先して実行していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
今回、新聞に、また別ですけれども、虐待相談の通告が最多の3,164件ということを見ました。相談の後の対応はスムーズにされているのか、また課題などあれば教えていただきたいと思います。
○渋谷こども家庭局こども家庭センター所長 我々こども家庭センターのほうで虐待通告を受けた場合は、まずは虐待通告内容の分析、そのほか、あと関係機関からの情報収集を行いまして、虐待自体がどのような背景から起こったのかというところを探りながら、実際の家庭へのアプローチというのをしていきます。アプローチをしていく際には、やはり虐待の発生要因は様々ありますので、例えば経済的な要因があるのであれば、区役所の生活支援課であったりとか、何か障害でお困りのことがあれば障害サービスの導入が必要ないかとかというあたりのことを対象の世帯に対して案内、虐待再発防止に関する指導とともに、そういうようなところの案内しながら再発防止というところもつなげていっているところであります。
ただ、やはり世帯の中にはそのような各種サービスの案内を行ったとしてもなかなかサービスにつながりにくい世帯というのもありますので、そういうような世帯につきましては、関係機関と情報共有をしながら、しっかりその世帯を見守れる体制というのをつくって行っていっており、今後もそのような作業を行う中で虐待の再発防止というところにつなげていきたいなというふうに考えております。
○委員(さとうまちこ) 人員の方も充足されておりますでしょうか。
○渋谷こども家庭局こども家庭センター所長 こども家庭センターのほうで、児童福祉司、児童心理司の配置基準というのが国のほうで標準というのが定められております。令和7年度でいきますと、児童福祉司の配置標準につきましては87名であるところを、我々神戸市こども家庭センターのほうでは89名の配置がされておりまして、児童心理司のほうにつきましては、配置標準が43名のところ、同数43名が配置されておりまして、人数的には充足されておるというふうに考えております。
○委員(さとうまちこ) 仕事の内容というのが非常に厳しい環境もあるというふうに聞いております。例えば児相の相談窓口は非常に厳しいということで、慣れない新人の方が精神的につらくなることもあるというふうに聞いています。
そこで、児相の相談窓口に関して、例えば最初に子供の発達については1番とか、よくある例えば養護についての相談は2番などと仕分をした後で担当者につないだりはしているんでしょうか。また、この電話は対応向上のため録音させていただいていますなどの対応などは考えられますでしょうか。
○渋谷こども家庭局こども家庭センター所長 電話、最初にかけてきていただくときに、一定最初の窓口で整理するというところは確かに業務負担の軽減につながる面はあるかとは思うんですけれども、市民の方が児童相談所、我々こども家庭センターのほうに電話をかけてこられる状態というのは、なかなか御自身でも相談したい内容が整理がつかずに相談されてこられる場合も多いですし、要因につきましても様々な要因が複雑に重なり合って起こっているということもありますので、最初の電話で番号で分けて整理するというところはなかなか難しいのかなというふうに考えております。
あと、2点目の御指摘の録音に関しましては、今現在録音ということはしておらないんですけれども、やはりかかってきた電話を全て録音するとなると、相談してこられる方の心理的なハードルが上がるという可能性もありますので、現段階ではちょっとそこまでは考えていないというようなところであります。
○委員(さとうまちこ) 例えば最初の相談というのは、やっぱりスピーディーに対応されたほうがいいかと思うんですけれども、2度目とか3度目というふうになることに関してはちょっと電話番号を御案内、別の番号を案内したりとか、そこでこういったことをできるのかなというふうに思うんですけど、そのあたりは検討はできないでしょうか。
○渋谷こども家庭局こども家庭センター所長 担当者がついたときに、その担当者宛てに直接かけるとかということは検討する余地があるのかなとは思うんですけれども、中には虐待のケースなどで、我々基本的には親権者と対応するんですけれども、親権者以外の方が担当者目がけて電話をしてくるというようなこともありまして、その辺なども考えますと、やはりある程度一旦は電話の受付というものが受けた上で対応方法をちょっと検討するといった流れも一定必要になってくるのではないのかなというふうには考えております。
○委員(さとうまちこ) 身近なところで、窓口で担当されている方が突然どなられたりとか、非常に厳しい言葉を受けたりして、鬱になって休職したというようなことも聞いております。現場の方にしっかり頑張っていただきたいのと、やはり現場の方々も守るということは大事だと思いますので、そのあたり何か今言ったようなことですとか、何か他の検討というのをされたほうがいいのかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。