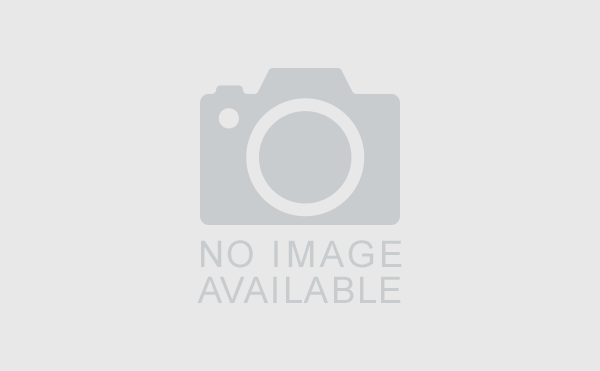こども家庭庁との意見交換③嬰児遺棄責任について
◾️さとう:嬰児遺棄については、こどもは一人で作れないので、両親同時に罪を問えないのか。遺棄するのは母親でという事は多々あり、一人で実行することとはなるが、遺棄をした女性にのみ責任を問われるのは不公平ではないかと考えるがいかがか。
法務省刑事局刑事課刑事局:遺棄行為をした人間が処罰の対象になる。(起訴例:父親との共謀)事情を知って遺棄することの関係が立証できた場合には、直接手を加えていなくとも共犯として起訴される。問題意識はあると認識はしている。刑事法の枠を超える。構成要件にあたるかどうかで刑事法では限界。不保護、家の中に置いたまま、何もしない(ネグレクト)生命身体に危険があったりで、背後に何があるのか必ず共謀を疑っている。法律自体を変えるのは難しい。家庭を顧みなく事件が起きても父親の責任は問えない。家族を福祉や行政の観点から、根本的な対策が望まれる。
<家庭を顧みなく事件が起きても父親の責任は問えない>
こどもは男女二人の行為によって誕生するものですから、因果関係は否めないと思いますが、刑法において問題になるのは結果(遺棄・死亡・行為)の法的な因果関係です。
性犯罪についてもですが、様々な刑法の見直しが必要だと考えます。
◾️さとう:0歳0日虐待もある。ワンオペ、ひとり親が安心して妊娠、育児できる環境がまだまだ整っていないと思うが、その辺りの見解をお聞きしたい。
こども家庭庁支援局虐待防止対策課:0歳0日の問題。現場の数値が右肩上がりできている。ここ20年ほど児童相談所での相談件数が上がっている。心理的虐待が増え、警察が面前DV目撃をしたお子さんについて児相への報告が増えている。令和4年度 実母から48%(ワンオペ、ひとり親など)次いで実父(重大な遺棄など)発生しやすい環境について、毎年死亡事例の検証をしている。原因として、予期しない妊娠。複雑な被虐待の生育歴 心身的な課題 養育能力の低さ、知的能力(見えない発達障害)がある。感情の起伏が激しい方、手帳を持つほどまでではない方など。精神疾患が1割ほど 経済的な状況が厳しい方が多い(非課税・生活保護世帯)孤立問題として、地域からの孤立は4割ほどで、親族からの孤立が15%ほど接触なしとなっている。行政につながってない方をどうするのか課題となっている。国としてやれるところは、行政につながった後のフォローすることと、その後の支援体制を整える。令和4年児童福祉法の改正があり、今年度から、こども家庭センターでは充実させたものを作ることが市区町村の努力義務となっている。妊娠期からの相談を受けながら、助産師が関わっていく。妊娠、出産後、母子保健、妊娠届出、スクーリングをし、養育環境が作れるのか、そこで孤立など さまざまの事情を聞き、保健師がフォロー体制を作る。また、妊婦健診の中、乳児検診で課題のある子を医療機関が気になった方を繋いでいく。出産後の乳幼児検診、不安の強い方、発達に課題のあるお子さんを把握し、関わっていくことと、こども相談支援拠点が十分に福祉的なサービスや対応に繋がってなかったという状況が出てきた。保健師と繋がりはあったものの、福祉に連携するなど、機関とつながっていなかった。合同ケース会議を頻繁に持つ、統括支援員という職種を置いて立体的な支援をし、アセスメント、状況、家庭状況、ソーシャルワーカー、心理職などで総合的に見ていく。令和8年度までに全国で創設。人員確保のための予算を組む。家庭支援事業の創設、拡充が今回の目玉。市町村は未然防止、その後は児童相談所で強化していく。
景気が良ければ、それぞれのご家庭で解決できそうなことは多々あるのですが、賃金が上がらないまま物価高、社会保険料の上昇、例えば国民年金保険料は1990年には月約8,400円が2020年には倍近くの16,540円ほどとなっています。戦争や感染症などの社会的情勢から食料品価格も急騰、エンゲル係数も上がっています。大学生はローン(借金)を抱えたまま卒業することとなり、夫婦それぞれに借金があれば生活も苦しく、子ども一人に2千万かかり、老後の備えが数千万必要だなんてい言われたら、出産子育てなんて考えられませんよね。
自分一人に力ではどうにもならないことを解決するのが政治と行政の仕事だと思っています。