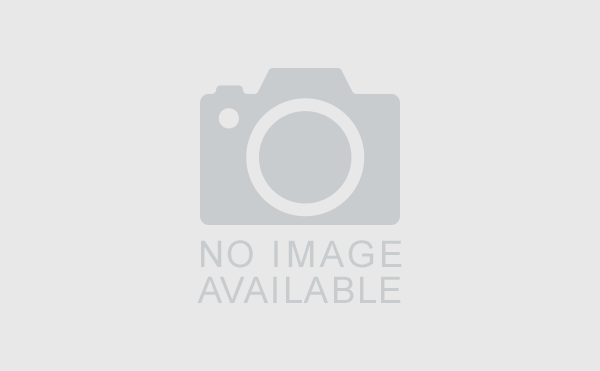2025/3/21苫野一徳先生による参考人聴取が実現しました!「学び/公教育の構造転換のビジョンとその実現に向けて」
不登校児童数の増加や、いじめ事案、教員の休職退職など学校現場が抱える問題は山積しており、こどもたちが多様化する中で、教師一人による紙ベースの一斉授業スタイルは限界に来ていると文科省が公表しているSociety5.0にもはっきりと出ております。教育の構造転換、自由進度学習を進めるにあたり、名古屋の山吹小学校、広島の常石ともに学園など視察し、考察を深める上でもできるだけ多くの教育関係者と共有したいと考えた末、現委員会において今年度中に実行したいと考えておりました、苫野一徳先生による参考人聴取がやっと実現いたしました。長くなりますが、非常に貴重なご講義をいただきました。皆さまにもお読みいただけたらと思います。
○参考人 初めまして、苫野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。着座で失礼します。
本日、「学び/公教育のゆるやかな構造転換に向けて」というテーマでお話をさせていただきたいと思っております。熊本大学の苫野と申します。
少しだけ最初に自己紹介をさせていただければと思うんですけれども、私、今熊本にいるんですが、実は出身は隣の芦屋でして、実は今熊本で単身赴任なんですね。それで家族は神戸に住んでおりまして、子供も神戸の小学校に通っておりますので、今日はこういった機会をいただけて本当にありがたいと思っております。
私は哲学者、また教育学者なんですが、哲学というのがここに書きましたとおり、そもそも考え抜くことでそれにまつわる問題を説く学であるということをいつも言っております。例えば「「自由」はいかに可能か」という本では、これは自由とは何か、あるいはよい社会とは何かという問いに答えた本なんですが、あるいは愛とは何かという問いに答えた本など、様々なその本質を考えて説くというのが哲学の一番大事な仕事なんですけれども、教育も、そもそも教育とは一体何なのか、どうあればよいと言えるのかというこの問いにまず答え抜かないと、教育の世界は特に信念の対立が渦巻く世界で、みんな教育については言いたいことがありますので、それぞれの教育観とか信念とか、あるいはほとんど趣味の次元で教育について対立が起こるんですね。職員室でもいつも起こるし、議会でもきっと起こるだろうと思いますし、国民的な議論の中でもいつも対立が繰り広げられてしまう。
そういうときに、そもそも教育って一体何のためにあるのか、どういう教育であればよいと言えるのかというこの本質を、やっぱりここまでならみんな納得できるという、そういった本質をまずはやはりしっかりと共有していきたいということで、まさに「どのような教育が「よい」教育か」という左上の本でそれを明らかにし、ではそれはどうすれば可能なのかということをこれまで様々な著作等で提言をしたり、それから様々な学校であったり教育委員会であったりと、学校づくりや授業づくりなどを現場で重ねるということもやってまいりました。
さとう委員長のほうから、本質観取についてもよかったらちょっとお話をとおっしゃっていただいたのもありまして、この後のテーマにも関係してくるんですけれども、子供たちとこの本質観取という哲学対話をかなりたくさん重ねてきました。
こちら、私の長女が小学校5~6年生のときに―― 今中3なんですけれど―― 夜寝る前20分とか15分間とかだけなんですが、本質観取の哲学対話をやったものなんですが、こういった様々なテーマについて、幸せとは何かとか、信頼とは何かとか、悲しいとは何かとか、かわいいとは何かとか、こういった問いについて、なるほどこれは言えてるねという言葉を、考え方をみんなで見つけ合っていくというのが本質観取という哲学対話なんですけれど、こういった本質を考え合って、みんながなるほどと言えるような考えにどこまでたどり着けるかというのがまさに哲学の命であり、こういった対話が実は子供たちともかなり深くできるんだということを、これまで長い間、子供たちと対話をしながら感じてきました。
実は、この本質観取が2024年度から、今年度からは小学校の道徳の教科書、来年度からは中学校の道徳の教科書に―― 光村の教科書に取り入れられることになりまして、これから何10万人もの子供たちがこの本質観取に取り組んでいくことになります。これは非常に希望があることだなと思ってまして、というのもこの本質観取、幾つもの意義があるんですが、当然ですが言語力・思考力・対話力が高まっていくというのはもちろんなんですが、私がやっぱり注目したいのはここなんですね。対話を通した合意形成ができるようになる。
幸せとは何かとか、自由とは何かとか、よく生きるとはどういうことかとか、こういったことをみんなで対話して、価値観も考え方も全然違う人たちが共に対話をする中で、それは確かにそうだねと言い合っていける、この経験を積むというのは、全くバックグラウンドが違う人も、価値観も違う、世代も違う人たちもこうやって対話をして合意形成することができるんだなという、この感触をつかんでいくことができる、もう本当に大きな機会になるなというのを感じています。
これはまさに民主主義の基本で、全く考えの違う人たちが、それでもなお対話を通して合意形成していけるというこの経験は、やはり本当に民主主義社会の成熟にとってもとても大事だなというふうに思っています。やっぱり表層じゃないんですね。本質を考えていくことができるようになる、こういった力を子供たちにどんどん育んでいきたいなと思っていまして、これが、またこの後で今後大事なこととして立ち戻りたいことですので、少しここでも御紹介させていただきました。
ということで本題なんですけれども、今日はこの3つを主にお話ししたいというふうに思います。そもそも学校は何のためにあるのか、この哲学的な土台をまずは改めて共有したいなと思います。
2つ目、今150年ぶりに―― 公教育が始まって150年がたちましたけれども―― 150年ぶりに学校が大きく大きく変わろうとしています。それはどのように変わっていけばいいのか、その具体的なビジョンとロードマップについてもお話ししたいと思います。
3つ目として、そのような構造転換が自治体規模で起こっていますので、それについても少し御紹介をしたいなと思っております。
ということで、最初に哲学的なお話で少し恐縮ではあるんですけれど、そもそも学校は何のためにあるのかということをお話をしたいと思います。これについては、実はもう何百年もかけて哲学者たちがずっと考え抜いてきて、そして実際に学校教育というものを構想しましたので―― 150年以上前にですね―― 実際には250年ぐらい前に学校教育、公教育は哲学者たちによって構想されまして、それから100年たって実際の公教育制度がつくられました。そこに行くまでにちょっとゆがみとかひずみも生まれてしまったんですが、それも含めてちょっとお話をしたいと思います。
まず押さえておきたいなと思うのが、公教育は人類1万年の戦争の果てに見いだされた革命的な発明なんだという、この学校教育の意義ですね。これを改めて共有したいと思います。
時間が限られていますので、今日はこのアプローチでお話をしたいなと思うんですが、実は戦争というものがこの2~3世紀かけて激減しているということが、様々な研究で明らかになっています。ただ、ちょっとにわかには信じられないですよね。これが前世紀と今世紀ですね、前世紀に2つの世界大戦があり、今世紀はテロで幕開けをし、そして今ウクライナ、パレスチナ、大きな戦争が今も続いてしまっている。戦争を、人類はむしろ、より苛烈にさせてきたんじゃないか、戦争や暴力で亡くなる人がどんどん増えているんじゃないかという印象を我々はつい持ってしまうんですが、大きく見ると右肩下がりで、戦争や暴力で亡くなる人の数というのは激減しているということが分かっています。
確かに、言われてみればこれが人類の歴史そのもので、ついこの前までは、人種が違えば奴隷にしたって当然と人類は思っていたわけですね。宗教が違えば殺して当然というふうに思う時代をずっと生きてきたわけですよね。身分が違えば殺して当然―― 右上の、これはローマの剣闘士ですけれど、恐ろしいですよね、考えてみれば。これはローマ市民の最大の娯楽だったわけですけれど、人と人が殺し合うのを見て楽しむような感受性さえ人類は持っていた。本当に恐ろしいなと思います。
そう考えると、300年ぐらい前までの人類と今の私たちってほとんど別の生き物になったと言っていいぐらい、精神の大革命を起こしたんだというふうに私はよく言うんですけれど、本当に精神が大革命をやっぱり起こしたんですね。今、私たちはこれ見ておぞましいと思うんですね。ついこの前まではこれが当たり前だったけれど、今我々はこれをおぞましいと思う。
なぜそのような感性を持つようになったのかというと、遡ってみると、この2~3世紀の間に哲学者たちが民主主義というものを考え出して、みんな同じ人間だよねということを認め合いましょう、そういうルールの下で社会をつくりましょうということを、長い長い戦争の歴史を経てそういった知恵にたどり着いたんですね。そして、人種とか身分とか関係なくみんな同じ人間同士認め合い、そしてこの社会を共につくり合っていこう、そのことを学校教育を通して育んでいこうという、こういったことをこの2~3世紀でじわりじわりと実現させてきたんですね。
これはもうほとんど奇跡みたいなことで、そんなことを300年ぐらい前までの人類は思っていませんでしたから、今我々がこうやって自由に平和に生きられるというのは、長い長い―― 人類は1万年ぐらい大戦争を繰り返してきましたけど―― この大戦争の果てにやっとお互いを認め合う、その上で社会をつくり合うというところにたどり着いた。
これをヘーゲルという哲学者は、自由の相互承認というふうに言いました。とても大事な考え方だと思います。お互い対等に自由な存在として認め合いましょうね、そのことをルールにした社会をつくらない限り、いつまでも人類はお互いの自由を巡って殺し合い、平和をつくり出すことはできない。これは私は人類の英知の中の英知だというふうに思っています。1万年かかった戦争を終わらせるための、恐らく唯一の原理じゃないかなと思うんですね。
この考え方、お互い対等な自由として認め合う、その上で社会を共につくり合っていく。これがまだ、できて200数十年なんですね、この考え方にたどり着いてから。じわりじわりとこれが世界的に広がっていって、日本も曲がりなりにも民主主義国家になって少しずつ民主主義が成熟していきましたけど、まだまだ現在進行形のこれはプロジェクトで、これから100年、200年、300年かけてもっともっと鍛えていかなきゃいけないなというふうに思っています。
もう少しだけ、これは釈迦に説法でこんなことを申し上げるのはどうかとも思いますけれども、一応哲学的に、そもそも民主主義とは何かということをおさらいしておきたいと思います。大きく2つの概念で言えば、民主主義の本質をかなりクリアに捉えたことになると私は考えていますが、まず1つ目が自由の相互承認ですね。みんな対等に自由である。誰も特権者はいないわけですね。みんな対等に生存する自由、幸福を追求する自由、言論の自由、表現の自由、信教の自由、こういったものがみんな対等にあるんだと、これは改めて、この考え方は人類にとって本当に画期的な考えだったと、この大事さを改めてかみしめたいなと思っています。
もう1つがジャン=ジャック・ルソーが言った一般意思という考え方ですけれども、これは簡単に言うと、みんなの意思を持ち寄って見いだし合ったみんなの利益になる合意のことですね。この合意だけが正当な根拠となってこの社会をつくり合うんだと、これが民主主義の一番大事な考え方で、一般意思の対概念を特殊意思といいますけれども、特殊意思というのは、ある一部の人たちだけの意思ですね。例えば権力者とか大金持ちとか、そういった一部の人たちだけの意思がまかり通るような社会であっちゃいけないよと、全ての人の利益になる合意を目指し続けるところにのみ民主主義社会の正当性はあるんだよとルソーは言ったわけですけれど、これも本当に優れた考え方で、確かになとやっぱり思わざるを得ない。
ただもちろん、一般意思を見つけるということはとても難しいことです。とても難しいことだけれども、それを目指し続けるところにしか我々の法とか権力というものの正当性の根拠がないということですね。当然、国家には、社会には運営者が必要です。運営者が必要ですので議会が必要ですし、行政が必要ですし、司法が必要ですよね。だけれども、こういった権力というものは必ず権力者が必要になってくるわけですね。ところが、この権力は必ず一般意思を目指すところにしか正当性がないんだというこのルソーの言い方は、非常に説得力がある。やっぱり現在なお、民主主義の一番根本的な原理と言えるかと思います。
この一般意思を目指すところにのみ、この社会の正当性の根拠があるとすれば、必然的に多数決は民主主義の本質じゃないということも導かれるわけですね。当然ながら多数決というのは多数者の専制に陥ってしまう可能性があり、少数者を排除してしまう論理ですから、多数決が民主主義ではないと。
これは本当に釈迦に説法の話なんですけれども、ルソーがとても面白いことを言っておりまして、ではなぜ選挙とか国会の議決とか議会の議決とか多数決が許されるのかというと、それは事前に全員がこれこれこういう場合は多数決で決めるということに合意しているからだと、合意していないと多数決を使っちゃいけませんよとルソーは言っていて、なるほどなと思わされますね。
なので、ちょっと脇にそれるかもしれないんですが、学校教育において多数決を使う必要はほぼないというのが私の経験です。例えば40人、30人ぐらいの学級で文化祭の出し物を何にしようかとか、修学旅行どこ行こうかとか、こういったときに多数決を使う必要はほぼなくて、みんなの意思を持ち寄って、みんなはこういうところに行きたい、こういうことをやりたい、皆で持ち寄って最終的にみんなが……。
こんな例がありました。文化祭で歌を歌いたいという人たちと、それからダンスを踊りたいという人たちとで分かれたことがあったんですね。多くの学校で、ここですぐに多数決を取っちゃうかもしれないんですけど、その学校では多数決が民主主義の本質じゃないということをちゃんと理解していたので、そこで対話を始めるんですね。そこから対話がしっかり始まって、どうすればみんなの利益になる合意が得られるかなというふうに考え合うと、A案とB案で多数決を取るんじゃなくて、A案とB案を考え合わせて、さらにいいC案をつくっていくという発想―― これはもちろん議会がいつもやっていることだと思いますけど―― そういうことをやって、最終的にミュージカルというアイデアになったんですね。これでみんなが、これはみんなの利益になる合意だとなった。
こういう経験こそ学校でやっぱり積むべきで、それこそ生成AIが出てきて、オンライン授業なんかも活発になって、学びそれ自体は学校じゃなくても学べるような時代になっちゃった。でもやっぱり学校は明らかに必要なんですね。それは民主主義を学ぶ場として明らかに必要で、民主主義を学ぶってどういうことかというと、こういう一般意思を共に見つけ出し合う、そして自分たちのコミュニティを自分たちでつくり合うという、そういう経験をたっぷり積めるのってやっぱり学校しかないんですよね。
そういう意味で、学校教育の意義が改めて浮き彫りになるんじゃないかなと思っておりますが、ともかくこうやって自由の相互承認を目指し、そして一般意思を見つけ出し合っていくというのが民主主義なんだということを、もっともっと子供たちにも共有していきたいなというふうに思っています。
まさにこの民主主義を実現するための制度的土台が3つあって、1つ目が言うまでもなく憲法ですよね。憲法によって全ての人の自由をルールとして保障するんだと、これもまた人類の歴史においてはとんでもない発明だったと言えるかと思います。
これもちょっと余談なんですが、私、教育学部でよく、憲法は誰から誰に向けて宛てられたものかということを学生たちに問うんですけど、6割、7割が間違えるんですね。これは本当にゆゆしきことだと思ってまして、先生になる人たちが憲法の本質を知らないというのは大変大きな問題だと思っています。国家が国民に与えるのが憲法だと思っている人が、結構若い人に多いんですよ。日本人はかなりの割合でそういう人が多いんじゃないかなって思います。
言うまでもなく、国民から国家権力に向けての―― 私も熊本市で教育委員もしているんですが、そういった公務員であったりとか議員であったりとか、そういったまさに権力に向けて宛てたのが憲法ですよね。全ての人の自由が必ず保障されなければならないんだ、全て国民は個人として尊重されるという、これは運営者の側が守らなきゃいけないんだというこの本質論を、若い人たちがこんなにも知らないというのは、これは教育の責任だなというのを非常に感じていまして、もっともっとこれを教育界に浸透させていきたいなと思っているところです。イロハのイなんですけれども、こういったところからちゃんとやっていかないとなと思ってます。
そして公教育ですね。憲法でどれだけみんな自由ですよと、みんな言論の自由を持ってますよとか、信教の自由を持ってますよとか、どれだけ憲法で全ての人の自由が保障されたところで、自由に生きるためにはやっぱり力が要る。読み書き算とかができないと誰かに支配されてしまうかもしれませんね。自由に生きるためにはやっぱり力が要る。
ここで言う自由というのは、もちろん言うまでもなくわがまま放題ということではなくて、他者の自由を尊重し、承認し、自らもまた生きたいように生きられるようになるということですね。そういう意味の自由ですけれども、ルソーはこれを社会的自由と言いました。他者の自由を尊重し、認め、自らもまた社会の中で生きたいように生きられるようになる、これが我々にとって大事な自由なんだと。
わがまま放題のことでは全くないわけですが、そしてまた、憲法がどれだけ全ての人の自由を保障していても、私たちの中にどんな人も対等に自由だというこの感度、この価値観、感受性というものが育っていないと全く意味がないわけですね。なので、ここで公教育が大事な役割を果たす。生きたいように生きられる力を確実に学校教育が育み、そしてまた他者の自由を尊重し承認する、そういった感動を育む、このために学校はあるんだということですね。
ところが、学校教育の力が及ばないところも残念ながらあって、障害とか貧困、いろんな理由でそれぞれの人が自由になかなか生きられない場合がある。そういう場合に、最後、福祉行政がキャップをはめる。この法と教育と福祉という3つによって全ての人の自由を保障していく、これが近代哲学者たちが250年ぐらい前に考えたプロジェクトだったんですね。
これは先ほど申し上げたように現在進行形のプロジェクトで、もっともっとこれを充実させていく必要があると―― 国内は当然、世界的にもこの自由の相互承認をしっかりと浸透させていくというのが、今後何百年かけてやっていかなきゃいけないことだというふうに思っております。
ということで、そもそも学校は何のためにあるのか。それは全ての子供に自由の相互承認の感度を育むということを土台に、自由に、つまり生きたいように生きる、その力を育むためなんだと、これが哲学的な公教育の本質ということになります。非常に抽象的な言葉なんですが、この抽象的な哲学原理というのが実はとても大事で、これが敷かれて初めて具体的なことを考えていくことができるようになる。ではどうすれば自由に生きるための力って育めるんだろうとか、そもそも自由に生きるための力って何なんだろうとか、今学習指導要領の改訂に向けた議論が進んでますけれども、本当はここから考えなきゃいけないんですよね。
そもそも自由に生きるための力って何なんだろう、自由の相互承認の教養って何なんだろうか、そういったところから指導要領というのはもう1度考え直す必要があるわけですけれども、それから自由の相互承認の感度ってどうやったら育めるんだろうとか、こういった一歩一歩、原理が敷かれて初めて一歩一歩具体的なことを考えていくことができるようになる、ここに哲学の意義もあるかなというふうに思っております。
ここまでちょっと抽象的な話が続いてしまいましたが、ところが現代は、この自由や自由の相互承認を妨げてしまう現象がいっぱい起こっている。ざっと挙げただけでも不登校は34~5万人、いじめもまだ絶えないし、体罰もまだ残っているし、私は小1プロブレムと間違って呼ばれている現象と呼んでいるんですが、これは小1のプロブレムというよりはシステムが生み出したプロブレムなので、これはシステムのプロブレムと考えたほうがいいと思っているんですが、あるいは落ちこぼれ、吹きこぼれであったりとか、嫌な言葉ですけど、あと同調圧力に苦しむ子供たち、空気を読み合う人間関係に苦しむ子供たち、理不尽な校則、様々な問題が今もなお学校にはある。
これをどうしようか、これを根っこからちゃんと問題を解決しなきゃいけないなということをずっと考えていまして、これをまずは誰かのせいにしちゃいけないなというのをいつも私は考えています。先生が悪いとか、親が悪いとか、子供が悪いとか、世間が悪いとか、教育委員会が悪いとか、あまり言い過ぎても問題は解決しないなということをいつも思ってます。
目を向けるべきはシステムであるということを私はいつも言っておりまして、150年間ほとんど実は学校教育システムって変わってこなかったんですね。どんなシステムかといいますと、みんなで同じことを同じペースで同じようなやり方で、同質性の高い学年学級制の中で出来合いの問いと答えを勉強するベルトコンベア型のシステム、これが150年間ほとんど変わってこなかった。
150年前は、これは1つのイノベーションではあったんですね。発明でした。というのは、ほとんど教育を受けたことのない子供たちだったわけですよね。そういった子供たちに一気に大量生産型で教育を与えていくためには、こういうベルトコンベア型の仕組みをつくる以外になかったんですね。なので、これは世界的にこのシステムが取られました。
ところが150年たって、このことが大きな大きな弊害を生んでいる。典型はこの落ちこぼれ・吹きこぼれ問題で、みんなで同じことを同じペースで学んでいくと、必ずシステム上、落ちこぼれ・吹きこぼれが生まれてしまうと。ついていけなくなる子が出てくるのは当然ですよね。その子に合ったペースで学べたら落ちこぼれる必要はなかったのに、あるいは例えば1週間ぐらい病気で休んじゃった、学校に戻ったらもうついていけなくなっちゃった、こんなことが起こってしまうわけですね。吹きこぼれもその反対の現象で、もう分かっててつまらないことを何度も繰り返し勉強させられて勉強するのが嫌になっちゃう、こういうこともたくさん起こっているわけですね。
あと、いじめ・不登校・空気を読み合う人間関係というのも、これは学年学級制という極めて同質性の高い仕組みが生み出してしまっているところがかなりあって、我々、今学年学級制は当たり前だというふうに思っていますけれど、これも150年前につくられた人為的な仕組みです。よく考えたら非常に不自然なコミュニティで、同じ年生まれの人たちだけから成るコミュニティって学校以外あまりないと思うんですね。これは非常に不自然な仕組みで、やっぱり同調圧力が高まるのは当然ですよね。
それから、出来合いの問いと答えをずっと勉強させられていたら、いつどこで何を学ぶか全部決められていたら、何でこんなことやらなきゃいけないんだって思うのは当然ですね。こういった様々な今の教育の問題はシステムに起因している部分が極めて大きいので、このシステムを根本からしっかりと、緩やかにですけれども、しかし確実に変えていきたいということで、ここから「学び/公教育のゆるやかな構造転換に向けて」ということでお話をさせていただきたいと思います。
大きくアイデアとしては、学びを変えていくということと公教育の仕組み全体を変えていくということなんですけれど、柱は3つありまして、まず1つ目が学びの構造転換と私が呼んでいるもので、学びの個別化・協同化・プロジェクト化の融合へと学びの在り方を変えていこうということになります。
2つ目は、今日はちょっとお時間の関係であまりお話しできないんですが、自分たちの学校は自分たちでつくるという、そういう学校にしっかりと立ち戻っていきたい。これは民主主義社会の土台として当然で、少しだけ申し上げると、学校の校則とかは当然ながら、行事とか、あるいは授業でさえも子供たちが先生とともに対話を通してつくり合っていくという、こういう経験は、先ほど申し上げたように学校だからこそできることで、ここでその民主主義社会というのは当然自分たちの社会を自分たちでつくるという社会ですから、そういう市民を育むに当たって、学校はそういう練習ができなきゃ意味がないですよね。学校で自分たちのコミュニティは自分たちでつくるという経験をたっぷりつくらないと、自分たちの社会を自分たちでつくるという市民が育まれるはずがありませんから、学校はこの民主主義社会の土台を支える制度的土台として、やっぱりここは揺るがせちゃいけないと思うんですね。なのでそういった学校にもっとしていきたいということで、ちょっと今日はあまり詳しくお話しできませんが、これが2つ目の柱です。
3つ目が、多様性がもっとごちゃ混ぜのラーニングセンターにしていこうというアイデアなんですが、これについてはまた後で少しお話ししたいと思います。今日特に焦点を当てたいのは、この学びの構造転換ですね。学びの個別化・協同化・プロジェクト化の融合とは何かということなんですが、まず、今までは先ほど申し上げたとおり、みんなで同じことを同じペースで同じようなやり方で、でした。
これが落ちこぼれや吹きこぼれなどの問題を生んでしまっているわけですが、これを自分のペースで自分に合った学び方や場所で学べるようにしていくということ。同質性の高い学年学級制の中で学んでいたものを、時に学年を超えた緩やかな協同性の中で学んでいけるようにするということ、そして出来合いの問いと答えを勉強するというこれまでの仕組みを、自分たちなりの問いと答えを探求する、そんなプロジェクト型の学びを中心に学んでいくというふうに変えていくということで、言葉だけ聞いてもちょっとぴんと来にくいので、この後具体的な事例を御覧いただこうと思うんですが、少しその前に、こういった学びの構造転換を実現するに当たって、それをサポートするエビデンスは無数にあるんですが、ちょっとだけ御紹介すると、カリキュラムや授業が一律一斉的である場合、子供たちはせいぜい半分程度の時間しか学んでいないということが明らかにされています。
当たり前といえば当たり前ですよね。一方的にずっと授業を受けていたら、それは集中力が途切れるときだってあるし、自分のレベルに合わないときはもう何言っているかさっぱり分からない。そしたらその時間が本当に無駄になってしまうわけですね。こういったことがもう至るところで起こっているのが―― どうしても学校現場は一律一斉のカリキュラムや授業がメインだと、そういうことがやっぱり至るところで起こっている。
授業を見に行くと子供たちがつまらなそうにしていたりとか、つらそうにしていたりとか、みんなのやっている算数についていけないのが恥ずかしくて隠しながらノートに何か書いているとか、そういう子供たちにはよく出くわすわけですけれども、ではどうしたらいいかということもよく分かっていて、個々のペースやレベルに応じた学びが進められて、先生や仲間の的確なフィードバックがあれば、より短い時間で学力保障や向上に効果が大であるということも、様々な研究で分かっているわけですね。であれば、それをシステムに実装していこうということで、個別化・協同化・プロジェクト化は融合というのが大事なんですが、ちょっと便宜的に個別化からお話をしたいと思います。
その際の基本の発想が、人それぞれ学びのペースとか興味関心とか合った学び方、合った教材、心地のよい学習空間などは異なっているという、この、本来学びの基本なんですね。この基本をちゃんと我々が意識するということだと思います。
最近、ニューロダイバーシティという言葉が教育界でも少しずつ知られるようになったんですが、脳神経の多様性ですね。我々の脳神経というのは実は極めて多様で、どんな学び方がその人に合っているかというのは全く違う、それぞれすごく異なっているということが見えてきました。脳神経科学レベルでもそういったことが分かってきた。
ところが、今まで学校はやっぱりこれを統一してたんですね、ほとんど。そうじゃなくて、やっぱり自分たちに合った学び方を自ら追求できるような、そんな学び場にしていきたい。なのでこれらをできるだけ個別化していこうということで、自己選択や自己決定の機会を広げていきたいということですね。
ところがもう一方で、この個別化というのが孤立化になってはならないのは当然のことで、孤立して学ぶのでは全くないんですね。そうではなくて、緩やかな協同性に支えられているということが大事だと私はよく言うんですが、緩やかな協同性、つまり必要に応じて誰かの力を借りられるとか、自分もまた誰かの力になれるとか、こういう環境の中で安心してみんなの力を寄せ合って学び合っていくという、こういう場をつくることが大事だと。
この緩やかなというのも実は結構ポイントで、その協同を強いられるということも結構あるんですね、現場では、ここで協同しなさいと。あまりにも過剰な協同の強要というのが逆に協同を嫌いにさせるということもありますので、やっぱり緩やかな協同性をいかにつくっていくかというのは結構大事なことですね。
ということで、少しその具体的な事例を御覧いただこうと思います。ちょっとユーチューブの動画を御覧いただこうと思うんですが。一部御覧いただければと思います。
「子ども学びのコンパス」は後で少しお話をさせていただこうと思います。今のが学びの個別化・協同化・プロジェクト化の融合のあくまでも1つの姿ではあるんですけれども、名古屋市は5~6年ぐらい前から、こういった方向に学びの構造転換を自治体を挙げてやっていくということで、今少しずつ広がっているところです。大きな自治体なので全校展開までにはまだ時間がかかりそうですが、かなり成果が見られているというふうに思います。
こういった経験から、どうすれば自治体規模でこういった構造転換が緩やかに、しかし確実に起こせるかというのもだんだん見えてきたところもありますので、この後もしよかったら少しディスカッションもできたらいいかなというふうに思っております。
次に、学びのプロジェクト化なんですけれど、これは先ほど言ったような、みんなで同じことを同じペースで言われたことを言われたとおりにではなくて、自分たちなりの問いを立てて、自分たちなりの仕方で、自分なりの答えにたどり着く探究型の学びをカリキュラムの中核にしていくということなんですが、こちらも非常に総合学習で有名な伊那小学校という長野県の学校がありまして、こちらの例をまた少し一部動画を御覧いただこうと思います。
この名古屋の山吹小学校も伊那小学校も、もう何年も私は御一緒させていただいてるんですが、本当に子供たちが生き生きして学ぶ姿がもうとにかく印象的で、先生方もすごく楽しそうなんですね。伊那小等々について語っていたらちょっともう1時間ぐらいかかりそうなので、これだけちょっと御紹介したいと思います。
伊那小学校で大事にされている「子ども観」というのがあって、それが、子供は自ら求め、自ら決め出し、自ら動き出す力を持っている存在であるという、この子ども観がとても大事にされていて、いつも先生たちはずっと―― この後もちょっとお話ししますが、とにかくいい学校は対話にあふれてるんですけど―― この対話をずっと重ねている。日々の授業は本当にそんな子供の姿が見られるものになっているかというのをいつも先生同士で対話して、これは本当に子供が自ら求めた学びなの、先生が一方的に押しつけていないっていつも問い合うんですね。子供が自ら決め出した学びなの、自ら動き出してるの、先生が無理やり動かしてるんじゃないのというのをいつも先生同士が議論して、時には本当に激しい議論になるんですね。
あそこはちょっと先生、出過ぎたんじゃないみたいな。でも、いやいや、あそこは教師の―― 「教師の出」という言葉があるんですが―― あそこは教師の出が大事だったんだとか、こういうことをいつも議論して、その子供たちが生き生き学んでいる姿をどうやったらそんな環境を整えられるのかというのをいつも議論している。本当に尊いなと、私はいつも伊那小の先生方と話をしていて思います。
効果を実証して、今、我々研究者チームが学びの個別化・協同化・プロジェクト化の融合が効果があるかというのを、検証をずっと重ねているんです。これまでこういった実践がほとんどなかったんです、日本の中で。なので検証がなかなか難しかったんですが、今どんどんそういう学校が増えているので、検証をかけられるようになりまして、かなりよい効果が見られています。
学力は当然向上するんですね。さっき言ったとおり50%しか学んでませんから、一斉の場合はですね。自分のペースで学べると、より早いペースで自分の学びを深められます。これはやり方はあるんですけれども、下手をすると子供たちを苦しめることもあるので、先生も苦しむことがあるんです。
これはコツがあるんですね。こういったコツを―― ちょっと脇道に入ってしまいましたが―― 本当は今後教員養成や教員研修でしっかりと普及させていかなきゃいけないんですが、今そういった養成や研修がほとんどなされていないのはとても問題なんですが、これはまたちょっと次の課題ですね。ちゃんとやれば、学力はもちろん自己効力感や集合的効力感―― 集合的効力感というのは自分たちならできるというやつですね―― それから自己受容感―― 自分はオーケーと思えること、他者受容感―― 人のことを認められる、こういったものが飛躍的に向上するということが見えてきました。
School Transformation Networkingという一般社団法人を我々研究者仲間でつくったんですが、ここがScTN質問紙という、主体的、対話的で深い学びがどれくらい実現しているかというのを測定できる結構画期的なものだと思うんですが、そういうアセスメントツールをつくりました。今、文部科学省のMEXCBというオンラインシステムにこれを掲載しているので、どの自治体や学校でも無料でお使いいただけるんですが、この分析によって、こういった学びをやっている学校は非常に高い効果が見られるというのが見えてきています。
少しだけその質問紙の内容を御紹介すると、結構現場にとって衝撃的な質問内容になってまして、例えば、授業では、授業を進めるのは先生ではなくて自分だと思いながら学んでいるかどうかというのを5件法で答えてもらうということになってます。あるいは、授業では学習の方法やペースを自分で選んだり決めたりしながら学んでいるというような質問もあったりします。これはある意味で現場へのメッセージになるんですね。
こういう授業をしていく必要があるんだなというのを、このアンケートの項目から先生方が学んでいくこともできる。さらにこのアンケートの結果を踏まえて先生同士で対話をしていく。あまり、この授業を進めるのは先生じゃなくて自分だって思っている子供たちは多くないなということが見えてきたら、ではどうしたらいいかなということを一緒に対話していくこともできる、そういう現場支援ツールに実はなっているというところがあります。
ある、名古屋のこういった学びの構造転換をやっている学校で調査をしたところ、この真ん中の破線が全国的な平均なんですけれど、異様に高いんですね、やっぱり。異様に高くて、点線が24年の6月で、実線が1月……。ちょっと表記がどうかな。年度ですから、そうですね。なので、6か月、7か月ぐらいこういった実践を続けると、さらにこの3つのポイントがかなり飛躍しているということも見えていて、非常に高い効果が見られるなということを思っています。
とにかく全国平均に比べて圧倒的に高いですよね。個性化した学習、つまり自分たちで自分たちなりに学んでいるということが見えている、あるいは内発的な協同というのは、ちょっと小さくて見えにくいかもしれないんですが、内発的に人と協同しようとしている、やらされているんじゃなくて。
それから、相手への認知的共感というのがぐんと上がってますね。他者を尊重しようとか、こういったものがぐんと上がっている。やっぱり自己選択、自己決定が尊重されると、他者のことも尊重しようとか、それから自分が尊重されているなという感じが非常にやってくるんですね。こういった学びはとてもやっぱり意義があるなというふうに思います。
最後に、多様性がもっとごちゃ混ぜのラーニングセンターへという3つ目の柱についてお話をしたいと思います。これから学校は多様性がごちゃ混ぜのラーニングセンターになるということを私は長く言っているんですが、先ほど申し上げたように、学校ってちょっと同種性が高過ぎるんですね、コミュニティとして。学校が今、言わば社会の分断装置になってしまっているところもあって、本当はこの民主主義社会というのは老若男女問わずみんながごちゃ混ぜになって、対話を通して合意形成しながらつくり合っていくべき社会のはずなのに、学校がそれを妨げちゃっているところがある。
高校や中学や小学校の校種で分け、その間の交流があまりない。学年でも分けて、その間の交流があまりない。障害のある・なしで分けて、その間の交流はあまりない。なので日常的に高齢者の方々と接している中学生ってどれくらいいるかなとか、日常的に障害当事者の方々と接している高校生ってどれくらいいるかなとか、そういうことを考えるとちょっと心もとないなと思うんですね。
やっぱり知り合わないと、理解し合って認め合い、同じ仲間として社会をつくり合っていくという感覚を身につけるのってとても難しいと思うんですね。やっぱり知り合う機会をもっともっとつくらなきゃといつも思っていて、これをもっとごちゃ混ぜのラーニングセンターにしたいというのを20年来ずっと考えていたんですが、ついに公立でそういったごちゃ混ぜのラーニングセンターが登場してきました。
福島県の大熊町に、学び舎ゆめの森というこども園と小中一貫の義務教育学校、この0歳から15歳までが学び合う学びやができ、ここに地域の人たちも自由に参加できるので、0歳から100歳以上までが学び合うことのできる公立学校が登場しました。
大熊町は原発事故で全町避難になったところで、今もまだ帰還率が数%なんですけれども、もうとにかく学校づくりを中心にしてまちを復興させたいという並々ならぬ思いでつくった学校になります。ここはまさにごちゃ混ぜラーニングというのを1つのコンセプトにして、日常的に異年齢が入り混じりながら学び合っています。
例えば中学生の子が幼児に絵本の読み聞かせをしているようなシーンが日常的に見られるとか、中学生と地域の人たちが地域の課題解決プロジェクトチームをつくってプロジェクト型の学びに勤しんでいるとか、こういったことが日常的に起こっているんですね。この図書ひろばも地域の人が自由に使えて、日常的にごちゃ混ぜになりながら学び合っているという、そういう場所ですね。
さっきの個別化・協同化の融合というのをやれば、異年齢・異世代が共に学び合うことだって可能になってしまうんですね。そういった場を今後もますますつくっていきたいなというふうに思っています。特に地方なんかは、これは非常に可能性があるなと思ってますね。統廃合をどんどんしてますので、統廃合するんだったらもうこういうごちゃ混ぜのラーニングセンターをつくっちゃっていくといいんじゃないかなというのを、いろいろと提言しているところです。
最後に、自治体規模で動き始めた学び・公教育の構造転換のお話をしたいと思います。今、学びの構造転換に自治体規模で取り組むところが増えてきました。ざっと挙げて、私がいろんな形で関わらせていただいている自治体だけでもこれくらいありまして、恐らくほかにも私の知らないところがあるんじゃないかなと思います。今かなりの勢いで、自治体規模でこういったことが起こっています。
これは恐らく日本の教育史上初めて起こったことじゃないかなと思っています。というのも、さっきの伊那小のような実践というのは、やっぱりせいぜい学校レベルで終わってたんですね。学校レベルにすら行かないのがほとんどで、できても教室規模でした。そういった意識のある先生方が、自分のクラスではこういった実践をやりたいということでやられるということは、単発的にはあったけれども、学校規模というのも難しかった。だけれども、今学校規模はおろか自治体規模でこういうふうにしていこうということが起こっているというのは、非常に励みになる動きだなと思っています。
しかもこの自治体同士が何がしかの形でつながって支え合って刺激し合っているというのも非常に大きな特徴で、こうなるとドライブがかかっていきますね。そしてどこかのタイミングで閾値を超えていくかなと、学びの構造転換が一定めどが立つのが私は10年から15年後かなと思っていて、神戸市もぜひそこに関わって全国を先導していただけるとさらに弾みがつくので、この構造転換への道がさらに開けてくるんじゃないかなと思っていて、神戸市にも大変期待を、私はしております。何がしかの形でますます関わらせていただきたいなとも思っております。
今、4度目の正直という言い方もされるんですね。というのは、1回目に大正自由教育運動というのがありまして、大正時代にこういった学びを実現したいというふうに、世界的に実は起こった―― 新教育運動というのが世界的に起こりまして、その日本版で大正自由教育運動というのが起こりました。ところが、これはいろんな理由で頓挫したんですね。一番大きかったのは、軍国主義によって何が自由教育だということで弾圧されるというのが大きかったんですけど、あとやっぱり今とは違ってリソースが非常に乏しかったんですね。例えば1学級70人いたりとか、使える図書資料がごく僅かだったりとかすると、こんな個別化・協同化・プロジェクト化の融合みたいなのは、やっぱり現実的に無理だったんですね。でも、今はこのICT化があり、これだけ充実してますから、できる条件はもう完全に整ったと言えると思います。これが1度目でした。
2度目が戦後の教育改革だったわけですけれども、子供たちの主体的な学びを実現していきたいというのがあったんですが、高度経済成長ということもあって、それよりは殖産興業といいますか、とにかく集団主義的に産業力を上げていこうというところに重きが置かれたので、少しそこの動きが頓挫していったというのがありました。
それから、いわゆるゆとりの時代ですね。総合学習をつくって、総合的な学習でカリキュラムを組んでいこうということがあったんですが、これも様々な理由で、頓挫とまで言っていいか分かりませんが、やっぱり様々な反発があって時期尚早な面もあって、あるいは準備不足の面も恐らくあって、ちょっと下火になってしまったというところがありました。
今、4回目なんですね。条件は完全に整っているんです。さっき申し上げたとおり、インターネットの発展と生成AIの登場、こういったものを背景にすると、もう私の子供なんかも生成AIで勉強してますね。先生も家庭教師も要らない、塾も行く必要ないって言ってます。例えば、ちょっと難し目の英文をばーんとチャットGPTに投げて、これ中学生が分かるように文法を説明してと言ったら全部説明してくれますから、もう本当に変わりましたよね。こうなってくると、先生が子供たちに一方的に授業をするって、そんな必要ないよねという声は、これからますます大きくなってくるというふうに思います。
いろんな条件が重なってきましたので、4度目の正直はきっと起こるし、ここで起こらないともう二度と起こらないんじゃないかなと思っていますので、ここはかなり真剣に、実現に向けて頑張っていきたいなと思っているところです。
ところが、今申し上げたとおり、かなり動きが起こってます。自治体規模で動きが起こっているんですが、これまで頓挫してきた大きな大きな理由が2つあると思ってます。
1つ目は、そもそも何のための教育かということのコンセンサスがちゃんと取れていない、あるいはそこから議論を始めていないということなので、はやり廃りに流されて、結局そのはやりが終わるとしゅんとしぼんでいってしまうんですね。なので、今生成AIがとかいうことで公教育の構造転換をやろうとすると、必ずしぼむと思います。そうじゃなくて、そもそも何のための教育なのか、何のための学校なのかという、哲学的に言うと自由と自由の相互承認を実現するためなんだと、民主主義の土台なんだと。
学校って何のためにあるって言われると勉強するためってみんな言うと思うんですけれど、もちろんそうなんですが、それ以上に民主主義の土台なんだと、共にコミュニティをつくり合うことを学ぶ、こういったために学校ってあるんだという、この言葉がきっと今はより響く時代になっていると思うんですね、何のために学校があるのか。ここにちゃんと立ち戻って、そこから、では何をしていけばいいかなというのを一歩ずつ考えていくというこの本質論を欠いてしまうと頓挫する。これまではそうやって頓挫してきたと思います。なので、この本質論をしっかりと敷くというのがまず1つですね。
もう1つ、学校内に対話の文化や仕組みをつくるというのが何よりも大事だというのが、この10年ぐらい、いろんな学校や自治体で学校づくりをやる中で見えてきました。まず、一方的なトップダウンだけでやってしまうと、これもトップが変わるとすぐになくなるというのがよく見られる現象です。旗を振るというのは結構大事なんですね。トップが旗を振るのはとても大事なんですが、同時に対話の文化・仕組みを現場に整えないと文化が耕されない、土壌が耕されないというのがあって、公デザインというのがやっぱりすごく大事ですね。なので、常に本質を問いながら、ではどうしたらいいんだろうということを現場が自分たちで考えていく、こういう仕組みをつくっていくというのが何より大事で、今までこれがやっぱりなかったなと思います。
現場で対応の文化・仕組みをつくるというのがなかったから、結局一時のエネルギーはぼんとなったけどすぐに廃れていくというのがこれまであって、むしろ現場で熱が出て、地熱が何か発電していくみたいな、そういう感じをつくり出していく必要があるなというふうに思います。
名古屋はまさにそれをやろうということで、大きな自治体なのでまだまだ不十分ですけれども、先ほど映像に出てきたように学びのコンパスというのをこの前つくりまして、これはまさに最上位として、そもそも何のための市民社会であり教育であるかというところから押さえていこうということでつくったんですね。これをつくる過程でも、決して有識者と言われる人たちだけがつくったんじゃなくて、様々な関係者、そして子供たち、先生方、いろんな人たちが至るところで対話をやって、それを集約してこれをつくるということをまずやりました。実現したい市民の姿として、まさにこれは自由の相互承認ですね。自由な市民としてお互いを認め合い、共に社会を創造する。
では、そんな社会をつくれる子供たち、目指したい子供の姿はどんな姿か。緩やかな協同性の中で自立して学び続ける、そんな子供たちの姿を目指したいよね、ではどんな学びの姿があればいいんだろうか。自分に合ったペースや方法で学ぶ、多様な人と学び合う、夢中で探求する―― これは学びの個別化・協同化・プロジェクト化の融合に相当しますけれども―― こういった、まずビジョンをみんなで共有し、この出来た学びのコンパスをベースに、今至るところで―― 学校現場であったり校長会であったりで、いつもここに立ち返りながら、ではどんな実践ができるかな、自分たちの学校はという、こういう対話を今広げている。じわりじわりと根を張ろうという活動を今やっているところです。
あと大事なのが、この校内研修を対話ベースにしていくというアイデアなんですが、ちょっと時間がありませんので、もうこれはざっと行きますが、せっかく校内研修という場があるので、これを対話ベースにして先生同士が根っこを語り合い、何のための学校か、どんな学校をつくりたいのかということから対話をして、お互いに助け合っていくという―― すみません、ここはもうざっと言っちゃいます―― そういった校内研修をやっていくと、これも非常に有効であるということが最近見えてきました。
ということで、最後になりましたが、学び・公教育の構造転換を実現する鍵は、とにかく本質を問い合い、本質に常に立ち戻る、そんな対話の文化や仕組みを現場にどんどん根づかせていく、ここに尽きるなということを考えております。
最後に具体的な事例、今日は一部しか御紹介できませんでしたので、リンクなどをお持ちいたしました。ということで、少し時間を過ぎてしまいましたが、ありがとうございました。ぜひ議論をさせていただければと思っております。
○委員長(さとうまちこ) 意見陳述は終了いたしました。苫野様、ありがとうございました。