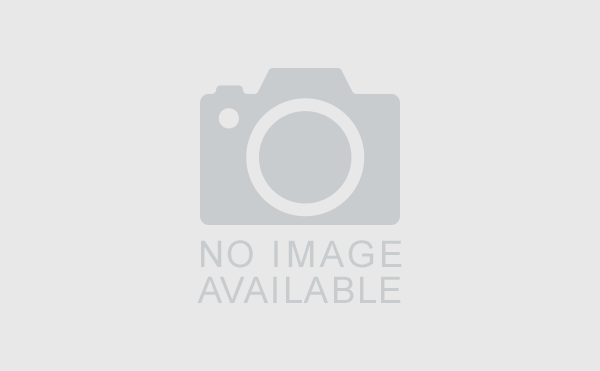令和7年予算特別委員会第3分科会〔7年度予算〕(こども家庭局) 本文 2025-03-10
学童保育の体制整備について・長期休暇中の学童保育における昼食提供について・保育士の人材確保について・こども医療費制度の拡充について・おやこふらっとひろば垂水などの駐車サービスについて・震災時のこどもの居場所について・バウンダリー教育・不就学児童の要望
- ◯分科員(さとうまちこ) よろしくお願いいたします。学童保育の体制整備についてです。
学童保育事業については、施設によって取組のレベルが大きく異なると感じております。各施設は、国の示す放課後児童クラブ運営指針、市からも、神戸市児童館活動の手引きの中で、放課後児童クラブ事業に関して想定しているとのことですが、現場では市のマニュアルが定着していないとも聞いております。市で定める規定を徹底し、必要に応じて規定を改めるなどにより質を担保する必要があるのではないでしょうか。
また、児童館であれば常勤の子育てチーフアドバイザーを全館配置済みとのことですが、学童保育に対する常勤職員の配置は十分にできているのでしょうか。館長のほかに1人の配置が基本となっておりますが、2人以上は配置したほうが望ましいと考えますが、併せてお伺いいたします。 - 152:◯中山こども家庭局長 本市の学童保育事業におきましては、平成19年9月に神戸の放課後児童クラブの基準──通称ガイドラインでございますけれども──策定をいたしまして、市内の学童保育のさらなる充実に努めてまいりました。
また、学童保育事業の運営主体である児童館におきましては、神戸市児童館活動の手引きを策定しておりまして、その中で学童保育事業の運営についても定めております。
各施設は、市のガイドラインや児童館活動の手引きに基づいて運営を行っているところでございます。
児童館活動の手引きにつきましては、基本的な考え方や保育の流れ、対応方法について記載しておりまして、国の新たな方針等に併せて必要に応じて見直しを行っているほか、新たに周知すべき事案や課題が生じた際は、その都度全施設への通知や館長会の場で周知を行うなど、学童の質が担保されるよう努めております。各指定管理者は、市が示した手引きや通知等をベースとしながら、独自のノウハウや創意工夫を盛り込み運営をしております。
常勤職員の配置ということでございますけれども、令和6年度からは全ての学童保育施設におきまして常勤職員を1名配置することとし、多様な特性を持った児童への一貫した対応や、気になる児童・家庭の早期発見等も期待できるほか、学校や地域との一層の連携も可能となるなど、安心・安全で充実した保育環境の提供につながることを狙いとしてこのような拡充を行ったところでございます。
令和7年2月現在、学童保育の常勤職員は全施設の約7割の施設に配置できております。配置できていない施設からは、適任の職員が見つからないなどのお声も伺っております。令和7年度の配置に向けまして、人材確保に努めていただいているところでございますので、引き続き、各施設での配置に向けまして働きかけを行っていきたいというふうに考えております。まずは常勤職員1名の配置に取り組むということが大切であるというふうに思っておりまして、その効果や課題を見極めていきたいと考えております。
児童館の手引きや基準につきましては、研修や会議等の場を通じまして指定管理者に説明を行っておりまして、指定管理者がそれぞれの職員への周知徹底を図っているところでございます。
今後も新たな国の方針や顕在化した課題に対して、新たな対応が必要な場合につきましては同様に取り組んでまいりたいと考えております。 - 153:◯分科員(さとうまちこ) 職員の方1人ということで、本当に施設側からしたらパズルのようにシフトを組むのが大変だということを聞いております。やはり2人ぐらい職員いたほうがシフトも組みやすいというふうな──余裕もできやすいということになりますので、これに関してはちょっとまた御検討いただきたいと思います。
そして、学童保育の実態につきましては、施設による体験格差が大きいと感じています。来年度は3か所でスポーツ体験事業をするとのことで、学童保育の質を高める取組と評価はしておりますが、一方で施設数が限定されることからさらに体験格差が広がってしまうことを危惧しております。
児童館であれば、全施設で特色ある取組を推進しており、全施設にインセンティブが当たるように予算措置しておりますが、学童保育でも同様の考え方が必要ではないか、お伺いいたします。 - 154:◯岩城こども家庭局副局長 本市の児童館では、各施設が指定管理制度の下、工夫しながら、花や野菜を育てるほか、ダンスや英会話など様々な特色ある取組を行っている状況でございます。
令和6年度より、地域のニーズに合わせた子育てプログラムの実施を促進できるよう、児童館の特色を生かした取組を後押しするインセンティブ制度を設けて支援をいたしております。インセンティブ事業のうち、小学生が対象の事業は、学童や一般来館の子供たちが参加できる仕組みになってございます。令和7年1月には、各施設の取組を紹介する事例発表会を開催するなど事例を横展開しており、その場には学童の施設長も参加をいたしまして、既に学童で取り組んでいる施設もあることから、引き続き他の施設にも広がっていくよう努めていくというふうに考えてございます。
それから、スポーツ体験事業ですけども、子供が外で遊ぶことは、危険予知、体力、創造力等の向上においても様々な効果があるというふうに考えられるため、令和7年度より児童館・学童保育施設において様々なスポーツの体験事業を実施して、子供の外遊びを促進していきたいというふうに考えてございます。具体的には、プロスポーツチームやプロトレーナー等を招聘いたしまして、定期的に様々なスポーツ競技の体験教室を実施していきたいというふうに考えています。同事業を契機といたしまして、スポーツ指導資格を持った地域人材の活用等により、各児童館における外遊びが広がっていくように努めていきたいと考えています。
引き続きインセンティブやスポーツ体験事業における好事例の横展開を通じまして、子供たちの体験がより充実したものとなるよう取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
以上です。 - 155:◯分科員(さとうまちこ) 学童は本当にいい場所だと思っておりまして、異年齢と交流もできますし、学校から家の間で気持ちの切り替えができる大事な場所となっております。今よく使われておりますデジタルデトックスの時間ともなります。時代の変化に伴い教育も変わりつつある中、学童保育も子供の成長に伴走する形を取っていただき、子供の自己肯定感を育むなどといった意識を持っていただきたいと思っています。
過去に学童保育中の事件もありました。子供たちをとどめておけばよいというようなことではなく、子供の成長は大人の成長にもつながります。質の高い充実した学童保育を目指していただきたいと思います。
以前に、京大のKuSuKuに視察に行きましたときに、本当にここから格差ってできてるんだなというふうにしみじみ感じました。今後少子化が進むとはいえ、学童保育のニーズは高まりますので、ぜひ子供たちが充実した時間を過ごせるような取組のほうを推進していただきたいというふうに思います。
次に、長期休暇中の学童保育における昼食提供についてです。
昼食は家庭弁当の持参が原則となっている施設が多く、保護者の負担となっております。来年の夏休みに向け、給食センターを活用した昼食提供を垂水区内の施設で調整中とのことですが、コンテナ規格等の問題で実施可能な施設が限定されると聞いております。給食センターから児童館への配送ができないとしたら、昼食時に児童館から学校へ移動して食べるなどによって対象施設を拡大できるのではないかと考えますが、現在の予定施設数と、今後どのように増やしていくのかお伺いいたします。 - 156:◯岩城こども家庭局副局長 中学校給食の全員喫食実施に当たりまして、令和7年1月より供用開始した第一学校給食センターの運営事業者より、自主事業として垂水区の一部の学童保育施設で給食を提供する提案がございました。令和7年度の夏休みの試験実施に向けては、給食センター稼働後間もないことや学校給食と利用人数等が異なる中での初めての取組となることから、同センターの有する調理設備を活用する試験実施を行った上で、今後の実施方法についても協議を行いたいという意向を事業者から伺っているところでございます。
給食配送に利用する食器や食缶を運ぶコンテナについては、衛生面や重量等の制約があるために、学童保育を実施する児童館、学校内コーナー等の現地調査を行っているところでございます。
委員御指摘のとおり、学童保育施設は給食コンテナを運び入れる規格になっていないことから、給食配送用のコンテナ以外でも実施できる方法がないか協議を今しているところでございます。
御提案のあった児童館等から学校等への配送可能な場所へ昼食時に移動して食べることによる対象施設の拡大については、喫食する児童も日々異なることから、給食を利用する児童のみを安全に児童館から学校まで引率する必要があるなどの課題もあることから現実的には難しいというふうに考えてございます。
実施に向けては、利用料金や注文受付、代金徴収、盛り付け、配膳に関する方法等について協議中であり、具体的な予定施設数も含めて詳細をお伝えすることは難しいですが、決まり次第施設と利用者に御案内をする予定でございます。
まずは令和7年度の試験実施に向けた準備を進めていくこととしており、実施状況や課題等を検証した上で、令和8年度以降の取組について検討していきたいというふうに考えてございます。
- 157:◯分科員(さとうまちこ) また子供たちや保護者の御意見を聞きながら進めていただきたいと思います。学校に近い学童もありますし、学校内の学童もありますので、その辺りを積極的に御検討いただきたいというふうに思います。
次に、保育士の人材確保についてです。
本市の保育士の平均年収については、「6つのいいね」等の処遇改善により、全国の保育士の平均年収を大きく上回っている状況ということです。年収は就労先を選択するに当たって大きな要因となると考えますが、人材確保に当たっては、「6つのいいね」等の取組は紹介していても、本市の年収が高いことは十分にアピールできていないのではないかと思います。
先月、こども家庭庁と直接意見交換をさせていただきましたが、こども家庭庁におきましては、保育士の人件費が上がらないということで、各保育施設において人件費がどれぐらいなのか、令和7年度から職員給与など経営情報の見える化が制度化されるというふうにお聞きしました。
本市としても年収の具体的な金額を明示し、人材確保に生かすべきと考えますがいかがでしょうか。
- 158:◯岩城こども家庭局副局長 本市では、国の制度に加えまして市独自でも保育人材確保策を実施しており、令和5年度の市内の保育士の平均年収は、本市の独自調査によりますと、全国の保育士平均を60万円上回る水準となってございます。
広報に関しては、一時金として7年間で最大160万円を支給や宿舎借り上げのための月額最大10万円を補助など、全国トップ水準の支援策をパッケージ化し、「6つのいいね」として効果的なアピールに努めてきました。その結果、近隣の市のみならず全国的にも神戸の支援策は手厚いという評判が高まっておりまして、市内施設における人材確保定着に寄与しているものと手応えを感じているところでございます。
関係団体からは、「6つのいいね」により職員の定着が進み、採用にかける費用や労力の縮減につながったと評価の声をいただいていますし、先日開催されました子ども・子育て会議の教育・保育部会においても、委員の方から、手厚い処遇改善により、保育士・幼稚園教諭の勤続年数が延びている、他都市で保育士をされていた方が神戸に引っ越して保育士をされるという話を最近度々耳にする、保育士の中で神戸市は働きやすいというイメージが広まりつつあるという、こういった御意見もいただいているところでございます。
今後、あらゆる業種・業界で人材の確保が厳しくなると予想される中で、保育人材確保のための広報の一層の強化が必要というふうに考えてございます。そのため、御指摘のとおり給与面のアピールも重要な要因と考えておりまして、令和2年度に実施したアンケートによると、資格保有者は保育士として就業するに当たり、働き方や人間関係など職場環境の改善、保育士としての仕事のやりがいや魅力も重視していることが分かっていることから、そうした要因も踏まえる必要があると考えておりまして、具体的な年収の明示までは考えてはございません。
一方で、委員御指摘のとおり、国は令和7年度から経営情報の見える化を制度化する予定であり、詳細はこれからでありますけども、モデル賃金等についても公表されるというふうに聞いてございます。これは平均年収ではありませんけども、これまで「6つのいいね」等の処遇改善に取り組んできた成果として、市内保育士の賃金水準が高いことが発信できるのではないかというふうに考えてございます。
今後とも保育人材の確保のために、養成校・関係団体と連携を図りながら効果的なアピールに努めてまいりたいというふうに考えてございます。 - 159:◯分科員(さとうまちこ) 本当に広報のほうよろしくお願いいたします。結局どれぐらいのスキルがあってどれぐらいの賃金頂けるかっていうのは非常に興味のあるところで、労力に見合わない賃金だったからこそ人材不足というものがありました。今後やはり低賃金に戻ってしまうと質も低くなりますので、このまま神戸市に頑張っていただきたいと思います。
そして次に、人材確保のためには職場環境の改善は重要であります。以前にも提案しておりましたが、保育士が職場環境を相談できる市の窓口を設置してはいかがでしょうか。 - 160:◯岩城こども家庭局副局長 人材確保定着を図り、保育の質の向上につなげるためには、働きやすい職場環境の整備が重要であり、本市では各施設の園長や主任を対象とした研修を実施しております。こうした研修を踏まえましてカウンセラーの配置や産業医との面談機会の提供を行っている園があるとお聞きをしております。
また、職員会議に非常勤職員も含めて全員が参加することにより、様々な話合いが行われるようになってございます。園内研修やオンライン会議システムやインカム等の活用によりまして職場内での連携がスムーズになった、ノンコンタクトタイム──いわゆる休憩時間とは別に物理的に子供と離れて各種業務を行う時間──そういったものが確保できるようになりまして、保育士同士で保育の振り返りができるようになったと聞いております。そうした改善事例についても報告を受けております。
職場環境の改善については、基本的には各施設で取り組む課題であると考えておりまして、市としては、引き続き研修の実施を通じましてサポートを行っていきたいというふうに考えてございます。
以上です。 - 161:◯分科員(さとうまちこ) 昨今、市内の保護者から不適切保育に関する相談を幾つもお聞きしております。保護者が不適切保育について相談できる窓口も併せて保育士の相談窓口、本市独自に設置して、園と保護者での調整が難しい案件になる前に保護者からの声を集めて早期に対応していただきたいと思います。
今るる御説明いただきましたけど、そこに見えてきてない問題のほうが多いんですね。やはり保育園というのは小さな社会でもありますので、その辺りを早期にすくっていただくほうが今後の職場環境の改善にもつながると思いますので、独自の保育士からと保護者からの直接の神戸市への相談窓口の設置というものは、私は必須だと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
そして、こども医療費制度の拡充についてです。
近年の本市の拡充施策として、高校生等通学定期券補助制度の拡充は、大阪府の高校授業料無償化による影響を意識したもので、保育料の引下げは政令市や近隣市の保育料との差を意識したものと聞いておりますが、そうであるならば、こども医療費制度についても近年、政令市や近隣市で拡充を進めていることから本市も拡充すべきではないかと思います。将来的には所得制限なしで高校生世代まで無料にすることが望ましいとは思いますが、まずは3歳未満までを無料としている外来助成について、就学前まで引き上げるなどの拡充を考えられないでしょうか、お伺いいたします。 - 162:◯中山こども家庭局長 こども医療費助成制度につきましては、本来国が取り組むべき施策でございますけれども、これまで県市協調事業として実施しつつ、市独自で制度の拡充を実施してきたところでございます。平成29年7月からは中学3年生までの子供の保護者に設けていた所得制限を撤廃しました。令和3年10月からは入院一部負担金の助成対象を高校生世代まで拡大し、令和5年10月からは外来一部負担金の助成対象を高校生世代まで拡大いたしました。これにより、高校3年生までの全ての子供が無料もしくは低額な一部負担金で受診できる環境を整えることができました。
兵庫県下の市町のうち、高校生まで医療費の無料化を行っているのは28市町で、そのうち7市町が所得制限を設けており、対象から外れる子供がいる一方で、神戸市は所得制限を設けておらず全ての子供を対象としております。政令市では、現時点で高校生まで所得制限なしで無料化を行っている自治体は2市のみと少数でございます。
各自治体を取り巻く環境や抱えている課題、財政状況は様々であり、限られた財源をどのような施策に充当するかは、各自治体の実情に応じて異なるものと考えております。
子育て支援施策は、医療費の問題だけではなく、児童虐待の対応、独り親家庭への支援、保育や学童保育ニーズへの対応など様々な課題があり、これらの課題解決を総合的に進めていく必要がございます。
こども医療費助成につきましては、このような子育て支援施策の総合的な取組を推進していく中で、子育て世代全体にかかる経済的負担の軽減や医療制度としての適切な給付と負担、さらには社会保障制度としての安定性、財政的な持続可能性などといった観点も考慮しながら検討する必要がございます。
こうした考え方に基づき、これまで制度を順次拡大してきたところでございますが、この制度を持続していくためには一定の御負担をいただく必要があると考えております。
引き続きバランスの取れた子育て支援策の検討を進めて切れ目のない子育て支援の充実に取り組んでまいりたいと考えております。
また、少子化対策の一環であるこども医療費助成制度につきましては、本来、国が取り組むべき施策であり、国策として持続可能な制度を確立するよう、国に対して引き続き要望していきたいと考えております。 - 163:◯分科員(さとうまちこ) 今まで、自治体とか、無償化について行った後の調査が行われております。無料化以前は経済的な理由で受診が遅れ、重症化してからやむを得ず時間外や深夜に受診しておりましたが、医療が無料になったことで軽症のうちに受診して重症化を防ぎ、時間外の受診が減少したということもあり、医師が無料だからと不適切な治療する事例は本当に極めて──ないということです。
これは、保護者は少しでも将来のための貯蓄──また物価高につき、以前より食費も多くかかる中、100円単位の節約をしております。子供たちの命と健康を守り、安心して医療が受けられると喜ばれているというこども医療費無料施策を実行しております政令市や近隣市では、拡充が進んでいることから、神戸市もより一層の努力をしていただきたいと思います。
高校の無料化につきましても地方の自治体がより全国に響いたということもございますので、ぜひ神戸市としても子育てにはなお一層の力を入れていただきたいと思います。
そして次に、おやこふらっとひろば垂水などの駐車サービスについてです。
おやこふらっとひろばについては原則区役所の1つの機能として利用者に対し、他の区役所窓口と同様に駐車サービスを行っております。
一方で、垂水区は区役所の中に入っておらず、児童館と一体的に運用していることもあり、駐車サービスを受けられないと聞いております。垂水区についても他区と同様に駐車サービスを実施すべきではないでしょうか。
また、市内3か所あるこべっこあそびひろばについては、駐車料金が必要ですが、これらも併せて駐車サービスを実施してはいかがでしょうか、御見解をお伺いいたします。- 164:◯丸山こども家庭局副局長 おやこふらっとひろばについては乳幼児健診や育児相談などで各区役所を訪れた際に気軽にふらっと立ち寄っていただいて、子育て相談や情報提供が受けられる場所として全ての区に開設をしております。
おやこふらっとひろば垂水は、御紹介いただいたとおり、児童館と一体的に整備運用しているものであり、駐車サービスを実施しておりません。他区と同様に駐車サービスを実施すべきとの御指摘ですが、おやこふらっとひろばは、ひろばの利用に合わせて児童館も利用可能となっていることに加えまして、立地もJR垂水駅前にあり、公共交通機関でもアクセスしやすい場所となっていることから、市外の方の利用も多く、おやこふらっとひろばの中でも特に利用者数が多い施設となっております。
一方で、垂水駅周辺は駐車場の利用や交通量が多い状況となっていることから、駐車サービスの導入については、立地や周辺の駐車場、道路等への影響などを総合的に勘案し、検討する必要があると考えております。
また、こべっこあそびひろばについてですが、こちらは就学前の親子が室内で思い切り遊ぶことができる場所として六甲アイランド、岡場、西神中央の3か所に設置しております。いずれも駅近くの公共交通機関でアクセスしやすい場所に設置しておりまして、市外の方の利用も多く、1日当たりの利用者数は各施設に200名程度と非常に多くの方に御利用いただいている状況でございます。
御提案いただきましたこべっこあそびひろばにおける駐車サービスの導入についてですが、導入に当たっての財政負担や行政サービスとしてどこまで提供すべきかといった観点も含めて、検討すべきものと考えておりまして、現時点では導入を予定しておりません。 - 165:◯分科員(さとうまちこ) 垂水区役所に用事がある場合は30分の無料駐車券が出たかなというふうに思っております。神戸市内の方に限って30分とか限定しながら、そういったところはやっぱり寄り添っていただきたいというふうに思います。
次に、震災時のこどもの居場所についてです。
令和6年の元旦に発生した能登半島地震の際には、地震発生の数日後に被災した子供たちの居場所を守る活動がすぐにできていたと聞いております。本市でも、南海トラフ地震等の災害が起きた際、早急に体制を構築できるよう備えておくべきと考えますが、日頃から災害を意識しながらこどもの居場所を実施しているNPO等の民間団体と連携しているのでしょうか、現状と今後の取組についてお伺いいたします。- 166:◯丸山こども家庭局副局長 昨年の能登半島地震におきましては、地震発生の数日後よりこども食堂の運営支援を行っている団体やこども食堂運営団体が連携して被害状況の情報収集を行うとともに、日頃の活動で培ったノウハウを生かして避難施設で炊き出しを行い、地震発生からおよそ2週間後にはこども食堂を再開されたと聞いております。
本市においても阪神・淡路大震災の際に移動児童館として児童館職員が避難所等に赴き、自分たちが持っている遊びの知識や技術を生かして、児童の心のケアを行うとともに、その後も地域ニーズに応じて青空児童館として活動を継続したという経緯がございます。
これを踏まえると災害発生時に市内に広がっているこどもの居場所が子供たちをはじめ、被災者の支援を行える場所になることも想定されますので、日頃からこどもの居場所運営団体において災害時の備え等を意識していただけるよう、情報共有などに取り組んでいくことは意義があると考えております。
現在、各区社会福祉協議会が運営するボランティアセンターにおきましては、災害ボランティア研修や災害時の地域における助け合い等を考えるボランティアの集いを実施しております。その際にこどもの居場所運営団体も参加して災害時対応について学ぶとともに、地域のNPO団体やボランティア参加者との顔の見える関係づくりを行っております。
災害時においては、まずは自身や家族の安全確保を優先していただくことが重要です。それから、活動の再開について、被災状況等も踏まえまして安全に活動が再開できる段階になってからということが前提にはなりますけれども、被災後において子供たちが集まれる居場所をつくることで心身の安定につながることも期待できます。
引き続き、こどもの居場所運営団体同士の交流会等の機会を捉えまして、災害時の対応について情報提供を行うなど、災害の備えとの意識を高めていただけるような働きかけを行っていきたいと考えております。
167:◯分科員(さとうまちこ) 能登でも日頃から連携があったからスムーズに居場所が確保できたというふうに聞いております。特に津波の被害などありそうな地域については重点的に連携を進めていくようお願いいたします。
次に、スマートフォンの適切な利用についてです。
先日、スマートフォンの使い方をテーマに布引中学校で中学生と高校生が話し合うフォーラムが開催されましたが、私自身も現地で見せていただきました。本当に、身近な年齢の高校生から学ぶことは非常に有意義なフォーラムでありましたので、取組を聞く予定でしたが、ちょっとお時間がありませんので──今後もネットで知り合った大人が信用できるのかとか、特殊詐欺の誘いであるとか、そういったことも教育委員会と連携しながら取り組んでいただきたいというふうに思います。
そして、いつも言ってることなんですが、未就学児の人権を守ることについてです。
これまで何度も申し上げているんですけれども、文部科学省も生命(いのち)の安全教育として各段階別の動画を作成しており、ぜひこれも御活用いただきたいというふうに思っております。
今、バウンダリーという言葉がありまして、それはやめてほしいとか、それは好きではない、距離を取ってほしい、それはバウンダリーだからということで、これをリズミカルに子供たちに復唱させているという動画もありました。これは嫌いな人であったり、知らない人など、好きな相手であっても、ときと場合で変わることがあります。自分も嫌と言っていいし、相手の嫌も尊重しなければいけない。言葉にして伝えることが大切で、それが人権の尊重となり、自分自身を守ることにもなりますので、ぜひバウンダリーについても御研究いただいて取り組んでいただけたらというふうに思います。
もう1つ、神戸にも外国人住民が増加する中、不就学児童もいるというふうに聞いております。
こちらも就学前に把握できるような対策のほうをお願いできたらと思います。