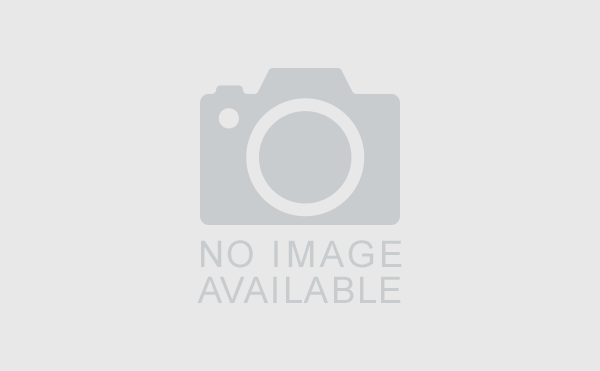令和7年度神戸市防災会議(第1回)の傍聴の感想
一昨日、9月29日に「令和7年度神戸市防災会議」があり、イタリア視察報告と書いてあったので、傍聴に参加しました。避難所の劣悪な環境については当選当初令和元年度から指摘し続け、令和3年度にはイタリアの避難所例を挙げ提案しておりましたので、どういった内容になるのかと期待を込めて傍聴しておりましたが、前に提案していた事が多く、、。議会で一生懸命指摘していても何年前とまだ同じような内容、、、と、少し残念に思いました。有識者の見解でないと響かないのでしょうか。
こちらに避難所対策を含めた2025年の一般質疑を載せておきます。
・余談ですが、この頃までは17番(大谷選手!)だったのですが、党員の離党などがあり16番となってしまったのは少し残念なことでした。(^^;
令和7年第1回定例市会(2月議会)2025-03-28
17番(さとうまちこ君) 続きまして、さとうでございます。よろしくお願いいたします。
最初は、神戸市の教育方針についてです。
子供たちが自分の頭で考え、判断して行動できるよう、子供たちが自信を持ち、より自由に生きていくため、学び、よりよい社会をつくるためにも、社会に出ていく力を育むという力を養うことこそが義務教育に求められると考えております。
昨今の社会情勢を見ても、主体性がなかったり、同調圧力が強かったり、工場生産性の昭和ながらの日本の教育には足りていないものが多いとつくづく感じる出来事が続いております。
150年ぶりに大きく教育が変わろうとしている中、昨年度策定されました第4期神戸市教育振興基本計画は、局別審査にて内容が総花的で変化を感じにくく、生徒や保護者、市民に伝わりにくいと質疑した際、まずは計画を広報し、関係者と共有するとの答弁にとどまりました。
不登校を喫緊の課題であると受け止め、教育改革、授業改革に真剣に取り組むのであれば、できるところからやるという消極的な姿勢ではなく、本市の教育が今変わるという大きなインパクトを持つ方針を策定し、積極的な姿勢を真に生徒や保護者へ、希望となるような、内外に響くようなアピールをすべきと考えますが、御見解をお伺いいたします。
次に、災害対策についてです。
令和元年第1回定例市会から、地域防災については避難所の環境改善について質疑を重ねてまいりました。質疑当時は、避難所となる施設では少しのお水とクラッカー、全員に行き渡らない毛布程度、そして翌年のコロナ禍においては妊婦に配ることのできるようなマスクの備蓄もなく、1万枚ほどあるマスクは全て期限切れ、令和3年予算特別委員会当時、生理用品の確認をした際、期限を切れたものについては順次廃棄をしているという実態もありました。
令和3年予算特別委員会においては、1980年、2,700人以上が犠牲になったイルピニア地震からの避難所の環境を飛躍的に改善された同じ震災国であるイタリアの例を出し、車椅子対応スロープつきトイレ、キッチンカー、特大テントで簡易ベッドが用意され、1週間程度で普通のベッドが来る、そして診療所も用意されるとお伝えしてまいりました。
避難所を運営する主体となる予定の防災コミュニティの高齢化に関しては、防災士との連携など、てこ入れの強化などの質疑も重ねてまいりましたが、今までにも避難所の環境改善については非常に時間がかかったと感じております。まだまだスタート時点でスピード感が足りないとも思っています。
近い将来発生が予想される南海トラフ巨大地震に向け、さらなる災害に強いまちづくりを進めていく必要があります。今現在、何が達成されたのか、また課題解決に向けた取組など、来年度より危機管理局に再編されますが、その再編により、今後どのように本市の災害対策を発展させていくのか、見解をお伺いいたします。
次に、神戸市の広報についてです。
本市においては、都市プロモーションや様々な個別事業について多額の広報費を費やしております。しかし、SNS時代において真に魅力があるよい施策やコンテンツは、利用者や関心を持ってくれた方々が広げてくれるなど、自治体が過剰な投資をして施策をアピールすることにどこまで意味があるのか、疑問が残ります。
例えば、203Xは多額の予算を使いながら誰に何を訴えるものがあるのか、よく分からない内容でした。東京においての広告ジャックもたまたま現地で見かけたものでしたが、内容も微妙なものだと感じました。MICEの動画も神戸のよさを出し切っていないと感じております。
対外的な広報は、効果の検証も必要だと考えますが、しっかりと検証されているのでしょうか。閲覧した方が神戸に来ていただいたかどうか分かるまで調べるすべがないようにも感じます。多額の広報費をかけるなら、効果の検証をしやすいものに集中すべきではないかと考えます。例えば、思い切って広報を吟味し、やめると効果が明らかになると思いますが、見解をお伺いいたします。
次に、遊休地の利活用についてです。
少子高齢・人口減少社会を見据え、既存ストックの活用が求められる一方で、限られた資源を最適に配分するため、活用するストックにおいては十分な吟味が必要であると考えます。
例えば、来年度予算において整備費用が計上されております兵庫運河周辺の市有地を活用した環境学習や周辺回遊の拠点施設については、地下鉄海岸線の活性化やにぎわいにもつながる有効な事業を考えます。
一方で、長年遊休地となってきた塩屋9丁目の市営住宅跡地について、公園的な利用を可能とするための設計費用などが計上されております。当該地は、急斜面であることから、全面的に有効活用するのは不可能に近く、また利用者も非常に限定されます。遊休地だからといって予算を組むことは慎重に検討すべきと思いますが、いかがでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
市長(久元喜造君) さとう議員の御質問のうち、私からは、災害対策につきましてお答えを申し上げます。
本市では、震災など過去の災害を教訓に、市民の生命や財産を守るため、自助・共助・公助による防災・減災対策を推進してきました。これまでも大容量送水管の整備や下水道ネットワークシステムの構築、防潮堤の整備、防潮鉄扉の遠隔操作化などをはじめ、地域での防災訓練や防災資機材の確保といった防災福祉コミュニティの活動への支援など、ハード・ソフトの両面で様々な対策を実施してきたところです。
今年度は、令和6年能登半島地震で顕在化した初動・応急期の課題に加え、阪神・淡路大震災後の経時的な社会情勢の変動やテクノロジーの進展なども踏まえ、本市災害対策のさらなる実効性の確保を図るために、全市を挙げて総点検を実施したところです。総点検の結果を踏まえ、令和7年度は、危機管理室を危機管理局とし、危機管理監兼危機管理局長の下で責任を明確化する体制といたしまして、様々な危機事象に対する対策を強化することとしております。
地域防災への支援といたしましては、防災福祉コミュニティの実情を把握するとともに、アンケートや個別ヒアリングを実施するとともに、有識者などによる検討委員会も開催しながら、各地域の実情に応じた効果的な支援方策を検討していきます。
避難所の迅速な開設と円滑な運営につきましては、各避難所へのキーボックス方式の導入や、避難所をスムーズに立ち上げるための必要資機材をまとめた避難所開設キットの導入などを進めていくこととしております。
さらに、市の初動・応急体制につきましては、職員に対する防災指令など、職員参集・動員方法の見直しを実施するほか、各種対策を着実に進めていきます。
同時に、先日開催されました防災会議でも専門家の方からイタリアの事例などを紹介していただきましたけれども、イタリアの対応、あるいは台湾の対応などに学ぶべき点もたくさんあると思いますので、御指摘を踏まえ、新たな視点も交えながら災害対策の強化を図っていきたいと存じます。
副市長(今西正男君) 私のほうから、2点御答弁を申し上げます。
1点目は、神戸市の広報についてでございます。
自治体の広報は、各事業の施策を単に発信するだけではなく、市のブランディング構築、あるいは市民とのコミュニケーション、国内外での認知度向上など大変重要なものだと考えているところでございます。
御指摘をいただきましたように、SNS時代におきましては、人々の関心を集めやすい施策が自発的に拡散されることもあると認識をしてございます。
一方で、情報が氾濫する現代社会におきましては、戦略的かつ効果的な発信を行わなければ、本市の魅力や施策の意義が適切に伝わらない場合が多いとも考えているところでございます。
そのような中、より効率的かつ効果的な広報を実施するため、実施した広報が誰にどう届いたかを確認し、その反響を検証することが重要であると考えております。そのため、ページ閲覧状況の分析ツールなどで閲覧者の属性や流入経路、その反応を分析、さらにはアンケート調査の実施など複合的な手法を用いて検証を行っているところでございます。
例えば、広報紙オンラインは、新聞のウェブ版のように定期的に閲覧されるということを目指しておりましたけれども、検索ワードでの流入とSNSの発信による瞬間的な流入が8割を占めるという分析結果でありましたので、その在り方を見直し、今年度で終了することとさせていただいたところでございます。
一方で、鉄道駅のデジタルサイネージで放映いたしました未来の神戸・三宮を描きました、御紹介いただいた203Xの動画では、動画を見たか、視聴後の行動などのウェブ調査を実施させていただいているところでございます。例えばJR三ノ宮駅での放映では、8割以上が検索などの行動を起こしておりまして、10代から20代ではSNS検索・シェアが多い傾向にありましたため、引き続き放映を継続しているという状況でございます。
また、SNS広告では、年齢や居住地、興味・関心など詳細なターゲティングを行いまして、クリック率や広告がどの程度行動につながったかを把握し、広告の最適化を図っているといったところでございます。
議員からは、広報を止めて効果をはかるという御提案もいただきましたけれども、やはり生じる機会損失や都市ブランディングの低下リスクのほうが大きいのではないかというふうに考えているところでございます。
むしろ、効果測定が容易な手法というものを強化しつつ、より戦略的な広報展開を推進することが重要だと考えているところでございます。今後もデータに基づく検証を行いまして、より効果的な広報となるよう努めてまいりたいと考えてございます。
2点目は、遊休地の利活用、塩屋9丁目の市営住宅跡地について御答弁を申し上げます。
人口減少が進む中で既存ストックの活用は重要なテーマでありまして、効果的な活用を図っていくべきだと考えてございます。
垂水区塩屋9丁目にある市営住宅跡地は、のり面崩落に伴う住宅解体後、長期間恒久的な利用がなされておらず、これまで事業者へのヒアリングなど調査・検討を行っておりましたけれども、まだ具体的な活用には至っていないという状況でございます。
現在、敷地の中央部を南北に周辺住民の方々が利用するツールとして活用しているほか、敷地の一部をまちづくり協議会である塩屋まちづくり推進会が花壇や果樹園の場として活用するなど、自主的に取り組んでいただいているところでございます。
一方で、長年利用されていないエリアも多くあるため、来年度は現地の測量を詳細に行うとともに、地質調査を行いまして、地盤の安定性の確認や防災対策の検討を行う予定としているところでございます。その上でということになりますが、大規模な施設整備ということは想定しておりませんけれども、現況の地形を生かしながら公園的な活用を検討してまいりたいと考えてございます。
当該地は、斜面地であるため、全ての土地が有効活用できるわけではありませんけれども、映画のロケ地に採用されるなどすばらしい眺望が望める場所でもあるわけでございます。
今後、このような現地の状況や特徴を踏まえ、また地域の意見を幅広くお聞きし、活用のプランを策定してまいりたいと考えております。
教育長(福本 靖君) 私のほうからは、神戸市の教育方針について答弁させていただきます。
第4期教育振興基本計画では、今後5年間、どのような教育を行い、どのような力を育んでいくのか、保護者や市民の皆様と共有し、進めていくために、新たな教育ビジョンとして、自他を大切に 自ら考え 未来をつくるを策定しました。それぞれの計画についても身近に感じていただけるよう、できるだけ簡潔にして重点化を図っておるところでございます。
また、特に何が変わるのだということでありましたら、先ほどから答弁の機会をいただいておりますように、これからの神戸の学びとしましては、個別最適な学びと協働的な学びの充実や実践的な英語教育の推進など、教員主導型から子供たちの主体性を大切にする授業への転換を図っていきたい、まずこれを大きく考えております。
また、教育活動全般にそれぞれの子供たちに寄り添い、ニーズに応えていくために、学校運営においてもこれまでのような職員室の中で決めていくものを決めていくのではなく、保護者や地域、企業、大学、NPOなど多様なスキルと経験を持つ方々が中心となっているコミュニティ・スクールを柱に据えて取り組んでいきたいと考えております。
それぞれの学校が目指す取組や方向性を具体的にタイムリーに学校便りや、すぐーるを使って発信し、関係者が当事者意識を高めてもらうことで効果的な広報になるよう努めていきたいと考えます。
17番(さとうまちこ君) ありがとうございます。
まず、教育に関してです。
名古屋は、人口233万ほどで神戸市とはまた規模が違うんですけれども、そちらでも山吹小学校、皆さんよく御存じだと思います。夢中になって目を輝かせる子供たちを目指して、個々に合わせる授業では発達障害の子供や同じことを一斉にやるのが苦手な子供も引け目を感じる必要がないということで、登校時間に差があるものの、学校に来られないという児童はいないというふうに、2年前ですか、お聞きしておりまして、今でも、今現在不登校児はゼロということをお聞きしております。
小学校につきましては、イエナプラン、推進してきたんですけれども、これ、実践されているオランダでは教員の働いている時間も短くなっているということもお聞きしております。そういったイエナプランを半分取り入れたような名古屋の山吹小学校、あるいは中学校においては草潤中学校のように、より自由度が高く、通常の学校では合わないと感じる生徒も選択肢とできると思います。学校が安心の場となるためには、公教育においてあらゆる手段を用意すべきと思いますが、いかがでしょうか。
教育長(福本 靖君) 現在、学校現場に多様な子供たち、いずれも不登校や発達に課題があるなど、本当に一斉授業では学びにくい子供たちが行っていることは認識しております。
先ほどからずっと答弁をさせていただいておりますように、やはりこれからは多様な子供たちが意欲を持って学べるような、そういう体制ですね。特に、授業の中身を変えていくということが大切だと考えております。
そのような授業改善と並行して、やはり学習指導員や地域団体、NPOによる放課後学習など、個々の能力や到達度に応じた学習支援に加えて、あと本年度から設置しておりますサポートルーム等を活用した個別支援など、個々の小さなつまずきを丁寧に把握し、的確に対応していきたいと、そのように考えております。
イエナプラン教育についても、その特徴となる異学年間の協力しながら自立心や自己有用感等の向上を図る活動は、例えば総合的な学習の時間であるとか行事等で部分的な取入れをそのような形で図っていきたいと思っております。
今後も児童・生徒の個々の状況に応じて意欲的に学べる環境づくりに努め、多様な児童・生徒を取り残すことなく、子供が主役の学びの実現を目指していきたいと考えております。
17番(さとうまちこ君) また、伊那小学校、これも公立なんですけれども、チャイムとかはなく、ヤギなどの動物と過ごしながら自ら学ぼうとする姿勢の生徒が増えているということで、北区にこういう学校があってもいいのかなというふうに思います。
そもそもサポートルームや学びの多様化学校がなぜ必要になるかというところは、もう教育長とも認識を共有しているとは思うんですけれども、やはり自由進度学習、非常に大事な取組であると思います。
個別最適とはいいましても、そういったふうに大きく、何が問題で何を変えていくのかということを大きく加賀市のように、例えばですけど、こういうふうな広報をするといろんな方の目を引くんですね。そして、今回の神戸市ですけれども、もう埋もれてしまっていると思うんですよ。何が大事といって、やっぱり授業が一番大事ですよね。そのあたりを変えていくんだということで教育長がしっかりと先頭切っていただいて、システムをつくっていただかないと、後に続かないということがあると思うんです。なので、システムづくりとして取り組んでいただきたい。
学期の途中でもいいと思うんですよ。困っているのは生徒本人です。今来ていない4,714人の小・中学校の児童・生徒、非常に大きな悩みを持っています。そちらに響くように。これだったらわくわくするなとか行きたくなるなというような、そういった呼びかけをしていただかないと、ほかのを進めていきます、個別最適にしますということでは、なかなか保護者や生徒には、特に不登校児童には伝わりにくいものだと思っておりますので、もしそうやって個別最適であるとか自由進度がいいというふうにおっしゃっていただくのであれば、ちゃんとお示しをしていただきたいというふうに考えております。
今の市内の不登校児童・生徒は、小・中合わせて4,714名で、本市が力を入れる校内サポートルーム、みらいポート、くすのき分校など、そこに通える生徒も非常に限られていると思います。やはりありとあらゆる手だてをするのは大事なんですけれども、授業改革のほう、しっかりと進めていただきたいというふうにお示しを必ずしていただきたいと思っています。
不登校に陥る原因として、教員の言動も大きな割合を占めているというふうにお聞きしています。何か問題が発生した際、教員へ指導できる信頼関係が築けておれば解決できる場面も多々あると考えます。生徒が安心して通いたくなる学校づくりのためには、教員の意識改革が必須であり、生徒1人1人と向き合い、安心して通える学級づくりのための研修を実施すべきと考えますが、見解をお伺いいたします。
教育長(福本 靖君) 子供たちとの信頼関係ですが、全ての教育活動において基本であると考えております。
現在、本市の多くの教員は、この原則を肝に銘じて職務に励んではいると思いますが、残念ながら、私も就任以来、この1年間、お困りごとポストやホームページへの苦情、それから学校現場から上がってくるトラブル報告などを受けた感想としましては、やはり児童・生徒や保護者と十分に信頼関係を構築できていない教員が一部いることも事実であろうと思います。
当然、多様化する価値観に非常に先生方が対応の難しいケースも常態化していると。だからこそ、逆に日頃の信頼関係が大切だと考えております。教員個人の質の問題であれば、的確な研修を繰り返す、チーム担任制などを導入するなどして幅広い対応を可能としていきたいと思いますし、その学校の組織の問題であれば、やはり学校長に対して根本的な改善を促してまいりたいと、そのように考えます。
要は、これらの取組を迅速に行うために、来年度は特に学校の現在地を多角的に分析し、把握できるように、教育委員会の体制を整えようと考えております。学校現場で問題が表面化してから後追いするのではなく、日頃からそれぞれの学校が今どのような状況なのか、特に児童や生徒との信頼関係は構築されているのかを、主事訪問や各アンケートの結果及び学校運営協議会等の議論を材料に的確に把握して効果的な指導や支援につなげていきたい、そのように考えます。
17番(さとうまちこ君) ありがとうございます。
私も今現在もいろんなお悩み相談を受けております。学校は、生徒に対して成長の変化を求めております。それに対して生徒が、それができない、追いつかないということで脅かされては安心感というものがなくなっていく、そしてチャレンジできる土台というのがなくなっていくんですね。
やはり教師が言ってはいけない言葉や今まで使っていた言葉でも注意を払うべきものもあります。例えば生徒の人格を否定することやほかの生徒との無意識な比較、そして褒めることもある程度過度な承認欲求を育てることにもなります。また、先生からほかの生徒の面前で皮肉やからかいなどの発言がありますと、周りの生徒もその生徒には言ってもいいことだというふうに認識され、差別、いじめにもつながっております。今までもありましたけれども、先生に我が身を振り返っていただき、今後十分に気をつけられるような研修のほうもよろしくお願いいたします。
やはり生徒は一人の人間ですから、何でも言うことを聞かすということではなく、対話を重ねながら自分の意見をしっかり聞いてもらえるというような環境をしっかりつくっていただきたいと思います。自分の意見がしっかり聞かれていると、他人の意見もしっかり聞いていけるような子供になると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
そして、職業体験というものがございます。
時間がないので、ちょっとはしょりたいと思うんですけれども、これも神戸市のほうでいろんな市内の関係部署にも訪れてもらう機会をつくったり、生徒たちが市役所の業務に触れる機会などをつくっていただきたいというふうにも思います。また、これ、もし時間があったら御返答をお願いしたいと思います。
名古屋市では、ロサンゼルスのキャリア・パスウエーから、障害や家庭環境、成績不振などがあっても様々な人生の道があり、希望を与えることとして大きく予算もかけ、キャリア教育に力を入れております。
理由は、自死される生徒の数を割りますと、中学校1校につき1人は自死を考えている、また予備の子供たちがいるということです。そこで、子供たちに楽しみや好きなことを考える機会を与えたいとのことでした。自分で意思決定ができない、自己肯定感を保てない、将来に希望を持てない、高学歴社会におけるモラトリアム傾向が強くなり、進学も就職もしないまま、考えないまま取りあえず進学したりする若者が増えているのは大きな課題であります。多様性のある子供たちの人生を豊かにするためにも、今後、キャリア教育にもしっかりと力を入れていただきたいと思います。
また、ある学校敷地内の柵の塗り替えを依頼したところ、予算が取れず、年度をまたぎますという返答がありました。それにしても景観を大きく損なっておりますので、ペンキの塗り替えは体験として生徒にやってもらうとか、あとそういった作業が得意な地元の方にお願いしてはどうかと提案した結果、周辺の学校の用務員の方々が集まっていただき、1日で仕上がることがありました。今後、こういった事例は共有しながら学校環境の改善を進めていただきたいというふうに思います。
そして、続きまして、災害についてです。
災害時の避難所について、市全体で南海トラフ巨大地震の想定避難者を約1万5,000人と見込み、避難所や備蓄物資を準備しているとのことですけれども、地域によっては十分でないところもあると考えます。
子供や高齢者を抱える家庭、要配慮者、そして体育館で過ごすことが困難な場合は、早急にライフラインが整った住戸に案内することが望まれるということを提案してまいりました。国の統計や市全体の数字で見るのではなく、地域単位で緻密に避難所のニーズを把握するため、市民に対して災害時に希望する避難先についてなどのアンケートを取るべきと考えますが、御見解をお伺いいたします。
副市長(小原一徳君) 神戸市におきましては、災害により自宅に戻れなくなった市民の方が一時的に滞在する施設として、市立の小・中学校を中心に指定避難所322か所を指定してきているところでございます。
また、発災当初から避難所における良好な生活環境の確保を進めるために、間仕切りテント及び簡易ベッドにつきまして、南海トラフ巨大地震発生1週間後の最大想定避難者数約1万5,000人分を現物備蓄することといたしまして、令和7年度中に配備を完了する予定としているところでございます。
神戸市の避難所におきましては、御紹介がありました妊産婦や乳幼児がいる家庭、高齢者、障害のある方で学校の体育館など一般の避難スペースでの避難生活が困難な避難者が安心して避難生活を送っていただけるように、多目的室や特別教室を活用いたしました福祉避難スペースを整備しているところでございます。
また、避難所での滞在、生活が困難であると各区の保健師等が判断した要援護者のために、市が二次的に開設する避難所として市内405か所の福祉避難所を指定しており、指定している施設には高齢者や障害者の入所施設などバリアフリーとなっている施設が多く、個々の避難者の状況に合わせて良好な環境で避難生活を送っていただけるように取り組んでいるところでございます。
また、御指摘いただきましたように、ライフラインの整った住戸への案内につきましては、市営住宅をはじめとする公的賃貸住宅の一時提供のほか、例えば被害が市内広域にわたる場合には東日本大震災や能登半島地震の際と同様に、国の依頼等によりまして他の自治体が提供可能な公営住宅等を入居希望者に提供することが考えられるわけでございます。
また、市民に災害時に希望する避難所等についてアンケートを取るべきという御提案もいただいたわけでございますが、市民の避難先など避難の在り方につきましては、やはり実際起こる災害の規模、また個々の被災状況等により臨機応変に対応していくことが望ましいと考えておりまして、避難先を固定化するようなことにつながるようなアンケートを実施することは、市民の方々に混乱や誤解を生じるのではないかと考えているところでございます。
今後も良好な避難所環境の整備を進めますとともに、市民に対しまして適切な情報提供を行ってまいりたいと考えております。
17番(さとうまちこ君) 性別であるとか年齢であるとか、どの程度の方が、言ったら最寄りの避難所にどれぐらい行くかということって最初に把握しておかないと、備蓄の数とか偏りとか出てくると思うんですね。それはアンケートを取る意義は非常に大きいと思いますので、区ごとでも取っていただければ、例えばモデルケースでもいいので取っていただけたらというふうに思います。 そして、広報についていかせていただきます。 広報に関しては、取捨選択の上、真に必要なものに限定していただきたいと思います。効果も分からず実施されている広報に対しては、限りある財源を捻出するくらいであれば、子育て・教育、そして市民福祉の充実、サービスの向上につながることに財源を使うべきと考えますが、あるいは新たに財源を確保する、例えば我が会派の原議員から検討の提案があった宿泊税を導入し、それを財源に観光施策のPR、広報を実施するのであれば、使途は明確であり、理解は得られやすいのではないかと思います。 福岡では、宿泊税による増収は28億円で、観光振興、そして広報や施設、お手洗いとか、充実に充てて、余剰は基金として積み立てているそうですので、ぜひ御検討のほうをよろしくお願いいたします。 そして、遊休地の活用なんですけれども、建設局については、ライフラインである道路の整備、非常に重要課題と私は考えております。特に塩屋は市道が多いため、破損したり凹凸が多かったりで、足腰に問題を抱える方やスーツケースを運ぶには難しいほどの道路となっております。公益性を考えると、遊休地もそうなんですけれども、市民の生活環境を整えるため、多くの方が利用する道路の補修を優先すべきではないかと思います。 そして、今回の未利用地については、震災後に補強し、30年経過、そして当時の資料がないということなので、検査の上、さらなる補強は必要だと思いますが、土地を地域に貸し出し、地元主体でクラウドファンディングや地域の方々に寄附していただくなど、費用を支えてもらうような手法も検討していただきたいと思います。 そして、子育てにおいての悩みは多々あるんですけれども、1人目というのは昔から変わってないんですね。結婚されて1人目を産むと。ただ、2人目を産むというふうに考え(この辺りで残り数秒となったことに気づきました)──非常に問題が起こるということなので、そのあたりしっかりと税の使い道、考えていただきたいと思います。