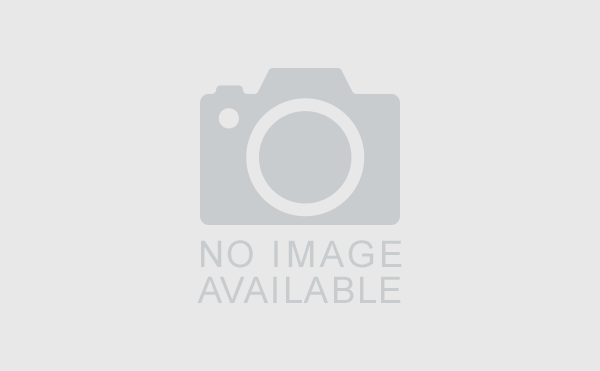人口ビジョンについて 令和4年決算特別委員会第1分科会〔3年度決算〕企画調整局 2022-09-27
少子化について、私は諦めていないんですね。人口減少を見据えた政策というものにもがっかりしています。2022年の質疑を見つけましたので再掲?しておきます。
ただ、施策というよりは、産みたい方が経済的理由により諦めることのない環境を整えることが大事だと思っております。
また、分科会は質疑時間が短いので、質疑を短くしたり途中で切ったりというような工夫も必要です。
- 分科員(さとうまちこ) 維新の会を代表いたしまして、前半は私、さとうが、後半は住本かずのり委員が質疑をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
まず、人口ビジョンについてお伺いいたします。
少子・超高齢化、東京一極集中、近隣都市への流出といった要因により、本市の人口減少は大きく進み、人口の150万人割れも差し迫っております。この喫緊の課題の解決に向けて、人口増加そのものを目標に掲げ、事業を進めていくべきであると思います。
神戸2025ビジョンに先立って改定されました神戸人口ビジョンにおいては、2060年までの人口減少の見通しが示されており、これに基づいて神戸2025ビジョンが策定されておりますが、ビジョン全体としても人口増加が数値目標とされておりません。人口減少に本気で取り組むのであれば、各事業において人口増加の目標人数を掲げ、より人口増加に効果の高い事業に行政のリソースを割くようにしていくべきではないでしょうか。事業の実施や検証、改善に当たり、人口増加につながっているかどうかという視点を意識していくべきと考えますが、いかがでしょうか。
- ◯辻企画調整局長 御指摘のとおり、将来ビジョンの策定におきまして、人口減少対策というものについては極めて重要な視点であると考えてございます。2015年の国勢調査の結果に基づきます神戸人口ビジョンの将来人口推計では、御案内ございました2060年には111万人まで減少するということで見込まれているところでございます。
こういった推計を踏まえまして、神戸2025ビジョンでは、人口減少対策を最重要課題として捉えて、他都市と差別化できるテーマ──海と山が育むグローバル貢献都市を掲げて、様々なまちの魅力を訴求する、また、将来を担う若者が神戸に集う施策を重点的に盛り込んでいるところでございます。
人口の増加目標の設定という御指摘でございます。出生数が過去最低を記録するなど、全国的に人口減少が進んできてございます。そういった中で、短期的に人口規模の増加のみを目標に掲げるということにつきましては、現実論としては難しいのではないかというふうに正直思ってございます。
先般発表されました令和2年の国勢調査では、全国で95万人ほど減少してございます。加えて、東京圏のほうでは約78万人増えていたと思いますので、差引き170万人ぐらい東京圏以外の人口が消失したということになります。また、令和3年の人口動態を見ましても、実際、全体9,000人のうち9割が出生・死亡に係る自然動態になってございます。
私といたしましては、やはり国策として、この出生数の増加なり、東京一極集中というものの是正には、国が率先して取り組んでいただくということがまず第一だろうというふうに思います。私ども自治体といたしましては、人口規模そのものだけではなくて、人口の移動ですとか年齢構成、こういったものを十分に分析しながら、域内経済の活性化なり、将来の自然増にもつながる社会動態、そういうものをつくっていく、増やしていく取組が必要かというふうに思ってございます。
例えば神戸市は政令市の中でも若年世代を中心に生産年齢人口比率が非常に相対的に低うございます。65歳以上人口比率が逆に4番目と、高いということもあります。そうすると、相対的に独り暮らしの65歳以上のお年寄りが多いということになってまいるんですけれども、こういったところもございますし、また、従業地・通学地に基づく昼間人口比率──これは平成27年の数字でございますけれども、102.5%、要は神戸市内に働きなり学びに来ていただく部分の率が102.5%、政令市では9番目ということで、大阪市と比べても30ポイント、また、京都市と比べましても10ポイント低いということでございます。
こうした観点から、やはり教育・子育て施策の充実はもちろんのことでございますけれども、20代、30代を中心とする若年世代の転入促進、それと定着、こういったものに資する施策、また、域内経済の活性化やまちのにぎわいにつながる昼間人口の増加に向けて、大学等の学ぶ場や働く場の創出に資する施策に重点的に取り組んでいく必要があるのではないかなというふうに考えてございます。
いずれにいたしましても、2025ビジョンの推進に当たりましても、各部局のほうで事業内容に応じた数値目標なりKPIを定めてございますけれども、今後も外部有識者で構成いたします神戸2025ビジョン推進会議や市会等で御意見を頂きながら効果検証いたしまして、取り組んでいきたいというふうに考えてございます。 - ◯分科員(さとうまちこ) 少子化、高齢化の進展によってさらに財政状況が厳しさを増すということは共通認識であると思いますので、今まで以上にやはり人口増加を意識しながらの、さらに実のある事業の実行をお願いしたいと思います。
理想を本当に大きく掲げて、がむしゃらに向かっていくのも良いのではないかなと思います。一説に、神戸市、200万人ぐらいが適当ではないかという話もありますので、また50年後の神戸ということを語るときに、それぐらいの人口がおったらええなぐらいの勢いでやっていただけたらと思います。
そして、神戸市からの人口流出の分析につきましては、いろいろアンケートを取っていただいたということで、3,000人分のうち500人の回答をいただいたということですが、より多くの方に簡単に御回答を御協力いただいたり、そして、転出の理由に関しても、やりたい仕事がないのか、それとも、それだけの収入を与えられる仕事がないのかということを詳細に記入していただいて、アンケートにもお時間を頂くので、インセンティブなども必要かと思います。また、そういったことで人口流出の原因分析と効果的な施策立案につなげるべきと考えますが、いかがでしょうか。 - ◯岡山企画調整局副局長 本市では、若年層の転入・転出理由やまちの評価等を把握・分析するために、平成28年度より毎年度、20代、30代の転出入者や在住者に対するインターネットアンケートを実施しているところでございます。調査ターゲットであります若年層の意見を効果的に集めるために、いわゆるQRコードを掲載した依頼はがきを転入者、転出者、在住者のそれぞれ3,000人程度の方に送付しておりますけれども、委員御指摘のとおり、効果的な施策立案に向けまして、より多くの御意見を集約、収集していくことが必要と考えてございます。
このため、今年度、2つの観点からアンケート実施方法の見直しを進めているところでございまして、具体的には、届いたはがきに目を留めてもらい、回答を促していくということで、デザインを改善していきたいなと思ってございます。2つ目に、回答の負担を減らすということとともに、より効果的な分析につながるための質問数、内容の精査を検討しているところでございます。
質問内容につきまして、これまでも年齢、居住地、家族構成などの属性とともに、移動のきっかけとなりました居住地の選択理由、まちへの評価など、一定有益な情報を得られているところではございますが、さらに、駅前のリノベーションをはじめとしました新たな施策の認知度でありますとか期待感等、神戸の強みをより伸ばす検討につなげていけるよう、見直しを進めていきたいと考えてございます。アンケート実施方法につきましても、これらの手法に限らず、様々な場面、手法で市民の意見を集めていくことは重要と考えておりまして、引き続き検討していきたいと思います。
今後ともアンケート実施方法や内容の改善を進めまして、在住者あるいは転出入者のより多くの声を集めていくとともに、様々な角度から分析を行いまして、効果的な施策立案につなげていきたいと考えてございます。
◯分科員(さとうまちこ) データというのは非常に大事で、高額でやり取りされるということもありますので、ある程度のインセンティブというのはつけてもいいのかなと思います。
そして、在住者アンケートの神戸市に住み続けたくない理由でも、子育てをする環境が整っていないという回答割合が多いと感じました。そして、子育て施策におきましては、本市でも様々な施策を打ち出し、支援に取り組んでいるものの、他都市と比べて伝わりやすい情報発信ができておらず、結果として、明石市や大阪市といった近隣市に比べて子育てしにくい、子育て費用がかかるというイメージにつながっているのではないかと考えます。
このアンケートですけども、住み続けたくない理由で、子育てをする環境が整っていないが断トツで多いという数を占めていまして、経済的な活気がないということも答えられております。そして、やはり子供の数が予定数に満たない、要するに育てにくい理由として、経済的負担が大きいというのが72%も出ております。
この神戸市に戻ってきたい──逆に神戸市に戻ってきたい理由としましては、地域の様子や雰囲気が気に入っているとか、生まれ故郷または親戚や知り合いがいるというざっくりした、ふわっとした理由なんですね。これはこれで、弱いといいながら、強みでもあるんですけれども、そういったところで、これ、片や明石市なんですけども、人口が9年増加、そして、9割の方が住みやすいということを出しております。これを大きくしたらよかったんですけど.
それで、予算と人も必要ということですが、この10年で予算倍増しておりまして、職員の数も3倍というふうに増えております。本当にうらやましい、いいことだらけやと思います。
子育て情報に限らず、神戸市に住むことの優位性やメリットに関する情報が神戸市への転入を検討する方に十分届いていないのではないか。住む都市としての神戸市の魅力や市の施策が他都市より優れている点について、神戸市に転入する可能性のある方、また、後押しのために、分かりやすく、より届きやすい形で発信する必要があると思いますが、いかがでしょうか。端的にお願いします。
◯藤岡企画調整局担当部長 私のほうから、今先ほど言われた魅力向上についてお答えさせていただきます。
先生がおっしゃった住み替え、引っ越しを検討されている方々に実際に神戸を住む場所として選んでいただくためには、居住地としての神戸の地域を具体的にリアリティーを持ってイメージしていただくことが重要であると考えております。神戸の生活に必要な情報などを盛り込んだポータルサイト、こうべぐらしを昨年3月に開設し、運用しております。このサイトでは、駅を基点としました生活圏程度のエリアごとに、実際転入いただいた方の生の声ですね、あと、学校とか医療機関、公園や図書館などの公共集客施設、あと商店街とか商業施設といった買物関係の施設、こういった生活に必要な情報など、暮らしに身近な情報を幅広く発信することを心がけております。
コロナ以降、リモートワークなど新しい働き方がノーマル化していく中で、居住に対する価値観の多様化も踏まえ、移住相談に対してはきめ細やかな対応──具体的には、個々の相談内容に応じた伴走型のコーディネート機能を充実化させていく必要もあると考えております。このため、先ほどのウェブだけの情報発信ではなく、個々の方のニーズに合った住環境エリアを紹介するなど、相談者に寄り添い、きめ細やかな対応をするため、今年5月にはこうべぐらしコンシェルジュを選任、設置しております。全国の移住住み替え検討者の方々からの問合せにワンストップで対応いただいているところです。
具体的には、コンシェルジュが相談を丁寧にお聞きして、お話していく中で、相談者の移住先に求めるニーズや思いを引き出しまして、適切なアドバイスを行い、本市の、先ほどのような切れ目のない子育て支援施策、良質な教育環境ですね、例えば街灯とか防犯カメラの設置による安全・安心なまちづくりの取組など、良好な生活環境の施策などのPRもしております。神戸への転入の動機づけの誘引を図っておるところでございます。
今後も移住セミナーなどにもコンシェルジュに参加していただきまして、大事なことは、移住者、検討者の立場に立ってですね、きめ細やかな情報発信を心がけてまいりたいと思っております。
◯分科員(さとうまちこ) そのこうべぐらしもそうなんですけれども、神戸市、すばらしいホームページもたくさんできたと思います。
そして、昨日もLINEの活用について提案させていただいたんですけれども、やっぱりホームページを検索して見るという時代ではもうなくなってきています。LINEで皆さんとメッセージ──友人やとか、知り合いとか、家族ともメッセージするときに、プッシュで来てくれたらすごいありがたいんですね。福岡市の例も言いましたけれども、LINEって必ず毎日1回は見るようなアイテムになってます。クラスの中でも1人のお母様が持ってなかったぐらいの勢いで使われておりますのでね。そこに、先ほどのこうべぐらしとかリンクできるようなワンボタンがあるだけでも全然違うし、そこで移住したいという方の後押しにもなると思いますので、ぜひLINEの活用というのを本当に進めていっていただきたいと思います。
そして、若者の神戸定着につながる企業の誘致の御提案なんですけれども、人口増加につなげていくためには、先ほどもずっと出ておりますが、若者に市内に就職していただいて、定住してもらうことが必要ですが、卒業後に就職を希望するような企業が神戸市内には少ないと感じております。やはり再開発を進める際に、多くの若者が希望するような、魅力ある、世界的に有名なIT企業などを誘致できたら、若者が集まり、そして相乗効果として、まちやその辺り、商業施設、活気づくのではないかと思っておりますが、オフィス誘致に関してはどのように神戸市としては取り組んでいくのか、端的にお願いします。
◯藤原企画調整局医療・新産業本部長 企業誘致ですが、先生御指摘のとおり、若者が就職できるような企業というのがあれば──大切だなというふうに考えてございます。御指摘があったIT分野に加えまして、アニメ、ゲームなどのコンテンツ産業、これは若い世代に非常に魅力があるということで、私どもも誘致に力を入れているところでございます。
誘致に当たっては、通常、家賃補助制度を設けておるところなんですけれども、令和2年度からは、このITコンテンツ産業に対して補助率を4分の1から2分の1に拡大するといった制度拡充を行いまして、これにより、令和2年度以降、56社を誘致しましたが、そのうち3分の1、18社がコンテンツ産業ということでございます。
こうした取組の中で、企業のほうからは、東京ではなかなか人材を確保するのが難しいと。逆に神戸のような大都市圏──人口が多いところで人材を確保できるのではないかというお声も聞いてございます。先生御指摘のように、今後、再開発で多数のオフィス床が生み出されることから、こうした企業のお声なども大切に聞きながら、こうした機会をチャンスと捉えて、引き続き若者に選ばれる企業の誘致に努めてまいりたいと考えてございます。
◯分科員(さとうまちこ) ありがとうございます。本当に、特に女性に人気のある企業の誘致などを意識していただけたらと思います。やはり女性がまちを歩くとにぎわいますし、それに伴い、商業施設等充実していくと思っております。
若者の定着に向けては企業への就職に限定されるものではなくて、神戸市はスタートアップ支援の取組もいろいろとされております。市内の大学生や高校生に広く市の起業支援情報を発信し、神戸で起業するという選択肢を示すとともに、学生の起業への関心を育成してほしいと思っております。
時間もありませんので、将来の起業家候補の視野拡大の取組についてお伺いしたいところなんですが、時間もちょっと少ないですので──起業家支援というのはいろいろされておりました。でも、それはやっぱりごく一部の方にしか恩恵がないように、やっぱりその一部の方だけのものになっているような気がします。
そこで、それを学生全体に伝えれば、それは多くの起業家を生むことにもなるかもしれません。神戸市内の学校などに広く周知していただきたいと思っております。やはり、ここは本当一番大事な部分だと思うんですけれども、そういった成功事例を広く学生、中学生、高校生に伝えることによりまして、起業する機運も高まると思いますし、将来の神戸を担う人たちに、入りたい会社がなければ起業ということが頭に入っていれば──そういう知識を持ったまま卒業していただけたらと思うんですけれども、これ、大学生、高校生に今はどういうふうに発信されているのか、限定的であるのかだけ、端的にお願いします。
◯垣内企画調整局新産業部長 委員御指摘のとおり、神戸に定着していただくためには、学生への起業の、どういう選択肢があるよというPRが必要だと思っております。これまでも、今年の7月から神戸市としては、これまでも学生に対する起業家教育をやってたんですけども、今年の7月からKOBEワカモノ起業コミュニティというのを新たに立ち上げて、様々な交流会や相談会を行っております。
PRにつきましてですけれども、より多くの若者、学生にPRをすることが必要だということで、ウェブサイトやSNSを通じた情報発信をこれまでも行っておりますけど、それに加えて、市内や近郊の高校や大学──具体的には高校6校、大学4大学に個別に訪問して、説明会を行ったり、兵庫県や金融機関と共同で学生向けのイベントを開催するなど、様々な手段で情報発信を行っております。今後は、兵庫県下の大学によって構成されます大学コンソーシアムひょうご神戸であるとか、各大学のキャリアセンター及び、各高校にも個別に案内を行っていく予定でございます。このような取組を通じまして、様々な起業プログラムをしっかりと若者に届けて、若者の市内での起業を促進していきたいと思っております。
以上でございます。
◯分科員(さとうまちこ) 高校を中退する子もいますし、中学校のうちにある程度のプレ知識みたいなのが備わってたらと思いますので、その辺りの取組のほうも考えていただけたらと思います。
以上です。ありがとうございました。