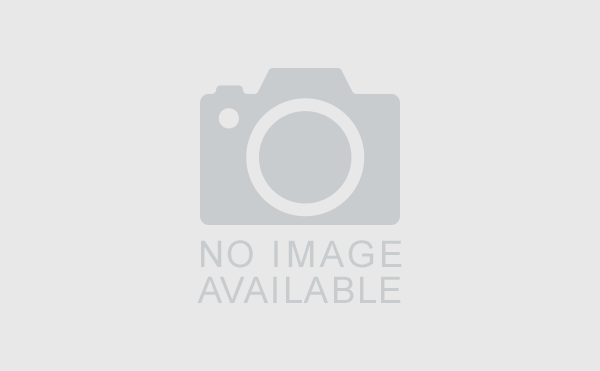2025/6/2教育委員会質疑(加賀市を参考に。自由進度学習について)
神戸新聞に出ていましたね。
2年前ほどから(当時は前教育長)質疑を重ね、やっと動いているという感じです。
「与えられる教育ではなく、自ら考え学ぶ。」
教育こども委員会
令和7年6月2日での質疑です。
委員長という立場で本来発言はできないのですが、最後の委員会だったので一言言わせていただきました。
以下、
○委員長(さとうまちこ) 他に御質疑ないようでしたら、私のほうから質疑がありますので、この間、進行を副委員長に交代いたします。
○委員長(さとうまちこ) 不登校児童のことについて質疑させていただきたいと思います。
神戸市は様々な施策をしていただいております。不登校についても様々な要因はあるんですけれども、学校側の原因について教育長の御見解をお伺いいたしたいと思います。
○福本教育長 不登校の要因はもう様々だということは、これは全国的なことでありますし、増えているということについてはやはりそれを選択するということが社会の風潮になっていることも大きいと思います。
ただ、それだからといって学校現場が手をこまねいているわけではなくて、やはりどうしたものかということを考えたときに、子供たちにとって魅力のある学校なのかということを考えるべきだと思っております。
先ほどのKOBE◆KATSUの質疑もありましたが、やはり今の子供たち、価値が多様化になっているから大変なんだ、それで済ますんではなくて、今の子供たちはいろんなことを情報を昔の子供たちに比べてたくさん持ってます。持っているからこそ、やはり自分たちでいろんなことを考えてますので、やはり昔のような画一的な学校ではなくて、それぞれの子供たちがそれぞれの能力を伸ばせるような、いわゆるウイングの広い学校をつくっていかなければ、今の不登校の子供たちも減らないのではないかと考えております。
そして、その大本は働き方改革もありますので、我々、今学校現場のほうには強く言っておりますのは、やはり朝、先生方の勤務は8時に始まって5時に終わると、その中で勝負をしようと、その中の勝負ということは何かというとやっぱり授業が中心になると思いますね。
行事でも当然部活動でも、本当に子供たちが輝いて、いろいろな価値を共有してきましたけれども、やはり授業をしっかりと、しかもどの学力層の子供たちもしっかりと参加できる授業に変えていこうと、これ非常に大きな転換でございます。
次期学習指導要領でもそのような形になっていくと思いますが、これは本当に一筋縄ではいかない問題だと思います。
よって不登校について対応することは何なんだと、教育委員会ということであれば、やはり各学校現場に対して、それぞれの先生方の子供との対応、その中の中心である授業をどう変えていくか、ここに注意していきたいと、そのように考えます。
○委員長(さとうまちこ) 先ほど教育長から一筋縄ではいかないという御意見がありました。
今、全国的にいろいろ教育改革が進んでおりまして、私たちも加賀市への視察も行ったりしました。私も山吹小学校、また常石など、様々見て回る上で、やはり授業改革ということが非常に大きなキーポイントになるんではないかというふうに思っております。
そこで一筋縄でいかない理由というのはどういったことが考えられるんでしょうか。
○福本教育長 私も長いこと教員をしましたので非常によく分かっております。もう学校の文化というのは、やはり前例踏襲が楽なんでございます。去年のことをしとけば怒られませんので、取りあえずやっとこうかと。でも子供たちが変化するスピードというのは相当早いわけでございます。
これも先ほどKOBE◆KATSUでもありましたが、本当に子供たち、明日でも学校の部活動というのは簡単になくなっていくというのが現状でございます。そのことについて子供たちもよく分かってまして、やはり私も校長時代、相当子供たちの部活動に関する考え方が変わってきてるなって本当にしみじみ思っておりました。そういうときに何ができるんかっていうのを考えたときに、やはりそれなりに対応は現場でやってきましたけれども、やはりなかなか前例踏襲の壁というのはなかなか打ち破れません。本当にやっぱりそれを打ち破るためには、やっぱり子供たちとよく話をする、理解をする、保護者とよく話をすると。ややもすれば、やっぱり学校というのはそういう保護者の声を聞いているふうで、いろんな過剰な要求があったらどうしようかとか、いろんな方向に行ったらどうしようかということで、なかなか聞けないようなこともありましたが、もうここは学校運営協議会等、本当に幅広く学校開いて様々な意見を聞いてやっていくと。一筋縄ではいかない理由というのはやはりそういう学校の文化が根強く残っていると、そういうことだと思います。
○委員長(さとうまちこ) 不登校児童数、年々増えておりますが、来年は減るとお考えでしょうか。
○西川教育委員会事務局部長 不登校の数ですけれども、これまで不登校施策につきましては、先ほど出ましたけれども、全小・中学校への校内サポートルームの設置でありますとか、学びの多様化学校みらいポートの開設など、充実した不登校施策を推進してきました。
本市の不登校施策につきましては登校のみを目標とするのではなくて、全ての児童・生徒に多様な学びの場を確保し、児童・生徒の意思を尊重し、児童・生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立できることを目指しております。
そのような中で、不登校児童・生徒数が減少することにつきましては、様々な施策を推進してきた成果の1つであると考えております。
近年、全国的に不登校児童・生徒数が増加し続けている中、昨年度から全小・中学校に配置された、先ほど申し上げました校内サポートルームの利用が増加し、出席の形、不登校児童・生徒数に変動が見られることも十分にこれから考えられます。
今年度につきましては、みらいポートを開校したことに加えまして、外出できない不登校児童生徒を対象とした新たなオンライン学習環境の提供、さらなる支援につなげるための不登校生徒の実態調査も実施する予定でございます。
今後も学校現場にとって効果的な支援ができますように不登校児童・生徒の支援に取り組んでまいりたいと考えております。
○委員長(さとうまちこ) ありがとうございます。本当に不登校児童数については、小学校のうちから多いというのが非常に気になります。
小学校で不登校になってしまうから、中学校も行きづらいというようなことが起きてはならないというふうに思っているんですね。
名古屋の山吹小学校、イエナプランとか取り入れまして、不登校児童数がゼロというふうにお聞きしています。もしかしたら数人の子はいるかもしれないんですけれどもゼロと言えるほどの成果を出していると思うんですね。そのことについて神戸市のお考えをちょっとお聞きしたいと思います。
○西川教育委員会事務局部長 不登校がゼロということは本当にすばらしいことであると改めて思います。ゼロの形に少しでも近づけていけますように様々な取組を展開しているところでございます。
みらいポートでありますとか、くすのき教室でありますとか、その他、様々本当に市としても施策を展開してますので、その中で、何とか子供たちの生き生きした姿がそれぞれの場所で見れて、例えば、出席認定の話にもなるんですけれども、そのあたりで頑張って、少しでもゼロの形に近づけるような、そんな施策を展開してまいりたいというふうに思っております。
○委員長(さとうまちこ) 今、お聞きした施策というのがどうも対症療法のような感じがするんですね。公教育は義務教育でありまして、子供たちは義務教育を受ける権利がございますので、それを学校とか教員が理由で不登校になってはいけないというふうにはもちろん思うはずです。
みらいポートも今1校しかございませんで、41名ということ、また西区や北区の子は選びづらいなというふうなことも思っていますので数も足りないんではないかと思っております。
また、いろんな不登校の要因ありますけれども、私たちができることは学校や教員の方々の意識を変えていただくということだと思うんですね。それで成功している他都市もございますから、そのことについて、もちろんみらいポートもあったほうがいいですし、サポートルームももちろんあったほうがいいと思うんですが、根本的な授業の改革についてちょっと今後のことをお示しいただきたいと思います。
○田尾教育次長 先ほども少し申し上げましたけれども、やはり子供たちが行きたくなる学校を我々としてはつくっていかなければならないというふうに思っております。その中で、さとう委員長がおっしゃるとおり、やはり授業をどう変えていくのかということは、もう私たちが今最優先で取り組まなければならないことというふうに、当然学校現場も我々も認識をしているところでございます。
学校現場に今発信をしておりますのは、やはり40人なら40人、学級の中にいる子供たちの中に、どこかに焦点を当てるような授業をするのではなくって、そこに、目の前にいる子供たちが、自分のペースで、あるいは自分が学び方をしっかりと選択をするというような幾つかの学び方を提供し、子供たちがそれを選んで納得できる学び方、そういった環境をつくっていくことが重要ではないかというようなことで、具体的な事例なども年度の頭に、現在、学びの推進課のほうから指導の重点といったものを学校現場にも示して、それを参考に、教員1人1人が、今年度どういったことを念頭に授業を改善していくのか、何を目標にしていくのかというようなことも、しっかりと目標を設定するというようなことで、学校現場には周知をしているところです。
我々といたしましても、そういった先生方の努力といいますか、それから工夫、そういったものを今年度は学びの推進課のほうが学校を全て回りまして、その実態を把握し、かつそれを把握して事務局として、またそれぞれ各学校の必要なところに事務局としては支援をしていくというようなことで、子供たちに対しても個別最適、そして学校に対しても個別最適な支援をして授業の改革をしていきたいというふうに思っております。
また、自由進度学習的な学習・授業なども幾つかの学校で既に先行的に研究をして、そういったものが市内の教員たちも、またそこに行って授業を見せてもらったりとかいうようなことで、非常に活発に動き出しているところですので、またそういったよい報告などもできるように努めてまいります。
○委員長(さとうまちこ) 家庭はいろいろ事情があると思うんですけれども、やっぱり、だったら学校に安心の居場所を感じていただきたいというふうに思うんですね。でも、安心ではないから、その4,700名ほどの児童が学校にも行けていないということ、事実があります。教員の方々の働き方改革っていうのはセットで考えていかなければいけないとは思うんですけれども、何よりも、もう前々から今の制度に合わない子供たちが困っている。また、その御家族が困っているということを念頭に置いていただいて、しっかりと抜本的で早急な改革の実行のほうをどうぞよろしくお願いいたします。
以上です。
○副委員長(平野達司) それでは、議事進行を委員長に戻します。
○委員長(さとうまちこ) 他に御質疑がなければ、教育委員会関係の審査はこの程度にとどめたいと存じます。
当局、どうも御苦労さまでした。
委員の皆様に申し上げます。
午前中の審査はこの程度にとどめ、この際、暫時休憩いたします。
午後2時より再開いたします。